親戚や身内、友人の葬儀に参列した事はあるかもしれませんが、葬儀を執り行うという立場になることは未経験であるという方が多いのではないでしょうか?
なかなか訪れないことではありますが、絶対に起こらないとは限らないのが葬儀を営むという事なのです。
しかも、結婚などのお祝いとごとは違い、十分な準備も出来ずに突発的に訪れるものです。
そんな葬儀をする際に困るのがお礼やお返しです。会葬してくれた方へお礼やお返しをしなくてはいけません。
きちんと感謝の気持ちを伝えて失礼の無いようにするためにも、マナー違反する事なく正式な様式でお礼、お返しをしたいものです。
今回はご自身が喪主やその家族になった場面でも冷静に確実に対応できるよう、葬儀でのお礼やお返しについて紹介します。
葬儀のお返しは二種類ある?会葬御礼と香典返しの違いは?

お通夜や葬儀に弔問に訪れてくださった方に対して返礼または返礼品を渡すことはご存知ですか?
お礼やお返しには二種類あり、会葬御礼と香典返しがあります。どちらもお悔やみいただいた方への返礼または返礼品ではありますが、意味と渡す時期が違います。
会葬御礼とは
会葬御礼とは、お通夜や葬儀に弔問に訪れてくださった方へお礼をする事、またはその品物を指します。
つまり、香典を頂いたか頂いていないかに関わらず、故人のために足を運んでくださった事へお渡しするお礼の品物ということになります。
ですので、会葬御礼はお通夜や葬儀の当日に準備しておき、弔問客へお渡しします。
香典返しとは
香典返しとは、お通夜、葬儀に来なくても香典を包んで渡してくださった方またはお供え物をしてくださった方へ、四十九日の法要が明けてからお渡しする返礼の品です。
最近では略式の風潮があり、地域によっては香典返しを即日渡しにすることもあるようです。
葬儀のお返しは何を選ぶといい?会葬御礼は?
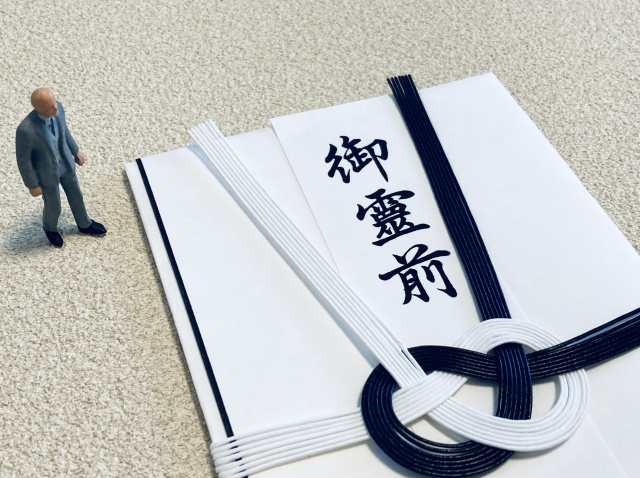
忙しい時間を割いて弔問に訪れてくださった方へ会葬御礼として差し上げるのにふさわしいのはどのようなものでしょうか?
会葬御礼は葬儀当日にご焼香のあと、お礼状とともにお渡しするのが一般的です。
返礼品としては不祝儀を後に残さないという意味から、いわゆる「消えもの」、日用品の中でも消耗品が良いとされています。
コーヒーや日本茶といった飲み物や、乾物や海苔のような日持ちのする食品、石鹸やタオルなどの日用品も消耗品として葬儀当日に差し上げる御礼として適切です。
会葬御礼の品物とともに小さな袋にお塩を詰めた、お清めの塩とお礼状を添えてお渡しします。
会葬御礼はお通夜や葬儀に参列していただいた感謝を表すものであるので、香典を頂いたかどうかに関わらず全ての弔問客へ差し上げるものです。
避けたほうがいいものとしては、当日持ち帰っていただくものなので、重いもの大きくかさ張るもの持ちづらいものは止めておいたほうが賢明です。
また、肉類も「四つ足生臭もの」と言われ、昔からタブーとされていますし、商品券やプリペイドカードなども金額が分かってしまうことから避けられています。
葬儀の会葬礼状のポイントと文例を紹介

大切な家族を亡くして慌ただしい中で。お通夜葬儀の準備の一環として会葬御礼の用意もします。
ここでは会葬御礼と共に弔問客へ渡す会葬礼状について紹介します。
会葬礼状はハガキ大の大きさのものがふさわしいでしょう。注意事項として以下のものがあります。
故人の名前の書き方
誰の葬儀に関するお礼状であるのか冒頭に記載しておきます。俗名であれば亡○(続柄)とするので、亡父、亡祖父などとし、故○○としても問題ありません。
宗教や宗派によって戒名がある場合には故人の名前と合わせて戒名を記載しておいてもよいでしょう。
名前の後の「儀」は読み方のない添え字です。故人に関するという意味で故人への謙譲表現です。
句読点をしない
お通夜や葬儀などの法事がつつがなく、とどこおりなく終わるようにと、句切れや文章が終わる意味がある「、」や「。」は使用しないようにしましょう。
季節の挨拶はせず頭語結語も不要
会葬礼状には季節の挨拶や頭語結語も必要ありません。挨拶をしないことは、あまりの驚きや悲しみに時候の挨拶も忘れてしまったという意味があるようです。
「拝啓」「前略」といった手紙の書き出しに使われる頭語は、それぞれ、「敬具」「謹白」という結語とともに用いられますが、会葬礼状においては不要です。
もし使う場合には、必ず頭語、結語を両方使い、片方だけになってしまうことがないようにしましょう。
忌み言葉、重ね言葉を使用しない
死や不幸を連想させるような言葉や重ね言葉は使用しない方が良いでしょう。
例としては、四(=死)や次々、重ねがさねなどです。言葉選びには十分に注意しましょう。
薄墨を使用する
会葬礼状を書く際には薄墨を使用するようにしましょう。薄墨には「きちんと力を入れて墨をすり、濃い文字で書くところであるが悲しみや驚きのために力が入らず墨が薄くなってしまう」や「悲しみの涙で墨が薄まってしまう」という意味があります。
会葬礼状の記入例
会葬礼状は葬儀が終わった後に渡すものですが、最近では通夜や告別式の受付時に返礼品と一緒に渡すことが多くなっています。
会葬礼状・葬儀のお礼状の文例
ここからは文例を紹介します。普通は縦書きですが、ページの都合上横書きにしています。
拝啓 亡祖母 ○○○儀 葬儀に際しましては
ご多忙中にも関わらず遠路わざわざご会葬を賜りご芳情のほど誠に有り難く厚くお礼申し上げます
早速拝趨の上ご挨拶申し上げるべきところ
略儀ながら書中を以って御礼申し上げます
敬具
令和二年○○月○○日
〒○○○ー○○○○ ○○県○○区○町○丁目○番○号
喪主 ○○ ○○
他 親戚一同
※時候の挨拶、季節の挨拶文は不要です。頭語結語はなくても問題ありません。
葬儀に参列せず香典・供花・供物だけ頂いた場合の文例
葬儀に参列されなかった方から香典、供花、供物をいただいた場合は次の例文を参考にお礼状を送りましょう。普通は縦書きですが、ページの都合上横書きにしています。
拝啓 このたびは 亡祖母 ○○○儀 葬儀に際しまして
ご多忙中にも関わらずご鄭重なる御厚志を賜り心より厚くお礼申し上げます
おかげさまで葬儀を滞りなく済ませることができました
茲に生前のご厚情に感謝申し上げますとともに
今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます
略儀ながら書中をもちましてお礼申し上げます
敬具
令和二年○○月○○日
○○ ○○様
〒○○○ー○○○○ ○○県○○区○町○丁目○番○号
喪主 ○○ ○○
他 親戚一同
※時候の挨拶、季節の挨拶文は不要です。頭語結語はなくても問題ありません。
上記ポイントを抑えて、弔問へ来てくださった方へ失礼のないように感謝を込めたお礼状を書きましょう。
葬儀後の香典返しのタイミングとふさわしい品物を紹介

香典返しは香典を頂いた方へお礼としてお渡しするものです。
古くは線香や抹香や花を故人の霊前に供えていたそうですが、現在では現金を香典袋に包んだものを香典と呼びます。金額は故人との関わりの深さに応じて変動があります。
香典返しは、本来は四十九日の法要の後に贈るものでしたが現在は略式化の影響もあり、葬儀当日に贈る即日返しを行う地域もあるようです。
喪の家族にとって、四十九日は「忌明け」であり、亡くなってからのお通夜や葬儀、四十九日の法要で弔事が区切りついて、一段落したところで御礼を行うという意味があります。
即日返しの場合はお通夜や葬儀の際に御礼をお渡しすることで、のちに香典返しの渡し忘れをしてしまうことを防ぐことが出来ます。
ふさわしい品物としては会葬御礼と同じく、日用品の中でも消耗品が好まれます。
最近は香典返しにカタログも人気があります。カタログ内の商品であれば、日用品以外でも忌み嫌われがちな肉類魚類などの生臭ものも問題ないとされています。
香典返しはいわゆる「半返し」が相場とされていますので、頂いたお香典の半分ほどの金額の物を用意して贈ります。
最後に
葬儀の際のお返しである、会葬御礼と香典返しについてご紹介しました。
やや紛らわしい所ではありますが、一度理解しておけば突然の不幸の時にも対応することが出来るでしょう。
故人を送り、葬儀を執り行う際に大切なことは、故人を思い葬儀に足を運んでくださった方へ不快な思いをさせず、失礼のないように御礼をすることです。
葬儀のマナーについて知らないという方は、これを機に少しずつ覚えていきましょう。
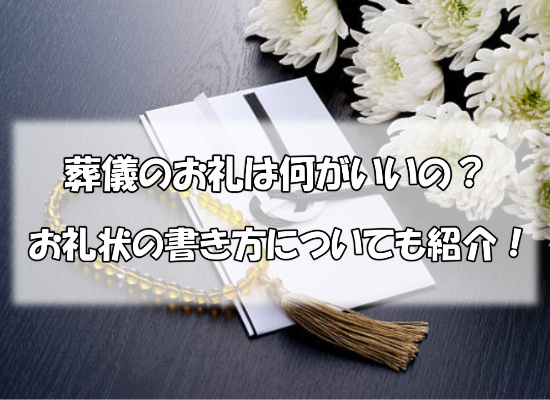


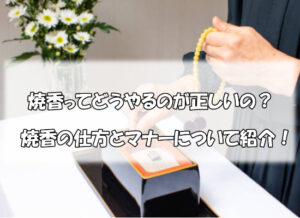
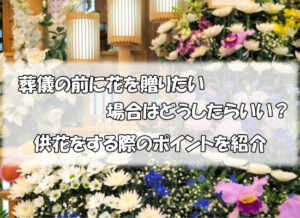
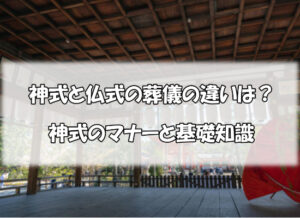
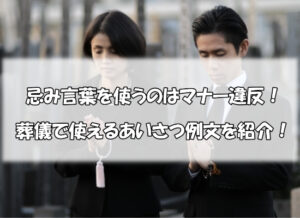
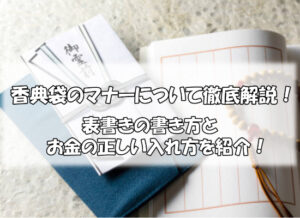
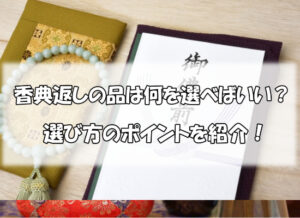
コメント