葬儀へはどのような服装・持ち物で参列するべきでしょうか?
通夜・葬儀などのお別れの儀式は、前触れなくやってきますので、いざという時に準備不足になってしまいがちです。
「社会人になったら喪服の準備くらいはしておきなさい」と家族や周囲から言われても、実際には葬儀に参列するような事はあまりないので、自然と後回しになりがちです。
年を重ねるにつれ、そろそろ喪服を用意しようと思ったとしても、その際の手提げは「どんなものでも大丈夫なのではないか」と軽視しがちなアイテムと言えるでしょう。
通夜・葬儀における手提げには厳しいルールはありませんが、故人や遺族に敬意を払い、不快な思いをさせないための最低限のマナーは存在します。
今回は一番後回しにされやすく、軽く考えられがちな、葬儀での手提げの選び方やマナーについて紹介させていただきます。
喪服における手提げの役割とは

手提げと聞いて、何が思い浮かびますか?
おばあちゃんが買い物に行く際に持っていくような小さな袋や、小学生がランドセルの他に手に持つ、副教材を入れるようなB4サイズほどの軽い袋が思い浮かんだかもしれません。
まず、手提げとは手に提げてもつ事、またそのように作られた袋、カバン、籠などを意味します。
手提げカバン、手提げ袋、手提げバックと呼び方は異なりますが、どちらも大きく口の開いた入れ物を指すことが多いです。
形の特長としては、袋の丈夫に主に二対の手や腕を通す半円形の取っ手があり、そこから手を入れて腕にかけるなどして持ち歩くことのできるカバンや袋、ハンドバック、トートバックを総称して手提げと呼ぶようです。
しかし、「手提げ」と聞いたときに、女性が喪服を着用する際に必ず持たなければならないハンドバックをイメージすることは少ないでしょう。
つまり、通夜・葬儀の場で喪服を着用する際の「手提げ」といえば、メインのフォーマルなハンドバックと一緒にもつ、サブバックのようなものと考えていいでしょう。
葬儀に手提げはメインバックとして使える?

さて、急は訃報を受けて慌てて家の中を探しても、フォーマルで使えるようなしっかりとしたハンドバックの用意をしていない場合、それらしい黒色やネイビー、グレーなどの手提げをハンドバック替わりにしても問題はないでしょうか?
もちろんそれ以外に準備ができず、急いで葬儀の場に行かなくてはならないとしたら、それは仕方がありません。
しかし、残念ながらそれではマナー違反になるでしょう。
葬儀の場では黒色以外の色は大変目立ちますし、目立たないということが葬儀の場での大切なマナーであるからです。
故人や遺族に不快な思いをさせない、失礼のないようにするには、きちんとした喪服用の黒色でフォーマルなハンドバックを持っていくのが正式と言えます。
「社会人になったら喪服の準備くらいはしておきなさい」と家族や周囲から言われる理由が分かりましたか?
葬儀の場で、恥ずかしい思いや故人や遺族に失礼な行いをしないように教えてくれていたのです。
このような状況にならないように、しっかりした葬儀用のバックをひとつ持っておくと良いでしょう。
紙袋は手提げ袋の代わりになる?

急なお別れのために、バックや手提げを用意できていない場合、紙袋は手提げ袋の代わりになるしょうか?
黒色以外の華やかなショッピングバックはマナー違反かなと感じることは出来るでしょうが、もしかすると黒色のショッピングバックであれば、これくらいは大丈夫だろうと考えてしまうかもしれませんね。
しかし、紙袋の本来の用途は買い物した商品を家に持ち帰るための袋です。
ですので、紙袋を葬儀用のサブバックの代用にすることは出来ません。
もし、家中を探してサブバックになるようなバックが見つからなかったとしても、黒色で地味なデザインであったとしても、高級店のブランドショッピングバックであったとしても避けた方かいいでしょう。
適切なサブバックがないからでしょうか、エコバックをサブバック代わりにする方も見受けられますが、カジュアルな感じが出ますし、やはり悪い方向へ目立ちます。
悪目立ちはマナー違反ですので、避けるのが賢明です。やはり、転ばぬ先の杖、日頃からの葬儀に対する準備が必要であることが分かります。
男性が手提げの必要な場合には?

女性の正式な喪服は小さいハンドバックですが、男性はフォーマルの場合には荷物はポケットに入れて手には何も持たない手ぶらが正式です。
葬儀に必要な物は、香典、袱紗、数珠、ハンカチ程度ですので可能な限り上着のポケットに収めるようにしましょう。
他には携帯電話とお財布程度ですので、見栄えが悪くならないように財布を小さくするなどの工夫も必要です。
万が一、荷物が多く、スーツの見た目が悪く不格好になってしまう場合や、その他にどうしても持って行く必要のあるものがある場合には、バックを用意しましょう。
男性が葬儀へバックを持参する場合の選び方として重要なポイントは以下の3点です。
手提げは不可
男性がバックを持参する場合は手提げではなく、小さめで邪魔にならないセカンドバックを選ぶようにしましょう。
手提げのトートバックのようなスタイルのバックはカジュアル感が強すぎますので、選ばないほうが賢明でしょう。
自分で管理がしやすいように片手で持つことができ、座った時に膝の上に置いたり、椅子の下に置いたり、そばに置いておけるよう小さめのセカンドバックを選びましょう。
色は黒色一択
バックの色は黒色のものを選ぶようにし、光沢のない素材で、金具が派手すぎずブランドのロゴも目立たないものを選びましょう。
見た目が派手でないことは葬儀の場においては大切なマナーです。
グレーやネイビーは周囲が黒一色の葬儀の場では目立ちすぎてしまいます。
喪服にふさわしい状態は手ぶらであるということを踏まえ、地味でシンプルなバックを選びましょう。
エナメル素材のものは光沢が強すぎますし、金具がキラキラしたようなのは適していません。
また、葬儀の場でカバンを開くような事は少ないかもしれませんが、開いたときに裏地が派手ということもないように、裏地にも注意を払いましょう。
革製品は避ける
男性のセカンドバックには、クロコダイルや爬虫類の型押しのデザインもありますが、葬儀の場では動物の殺生を連想させるような革の模様のバックは避けましょう。
また、本革もマナー違反です。合成皮革であっても見た目で判断がつかないので、避けたほうが無難です。
最後に
通夜、葬儀の場ではいわゆる手提げは、場合によってはマナー違反になってしまうこともあるので注意が必要です。
また、手提げをハンドバック全般として考えた場合には、男性のバックは案外と選ぶのに難しいという事が分かりました。
故人や遺族に失礼のないように、急な訃報に慌てることがないように、日頃から備えておきたいものです。
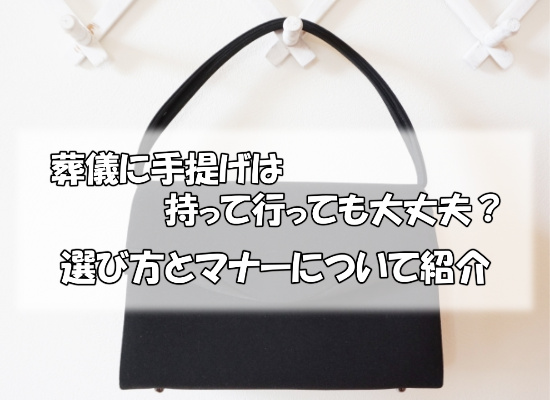


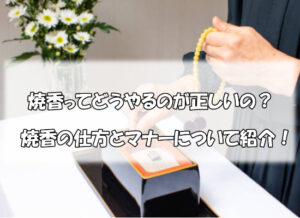
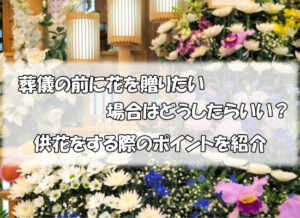
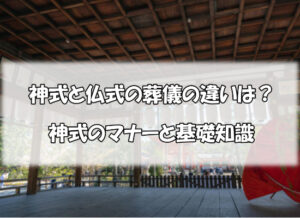
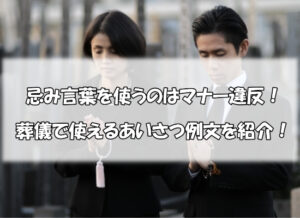
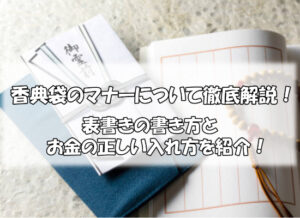
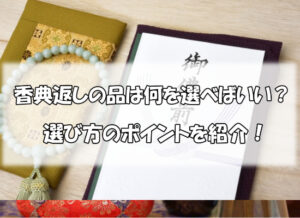
コメント