葬儀の場でポロっと出た言葉が、あとでよく考えたら葬儀に使うと良くない言葉っだったなんて経験ありませんか?
葬儀の場は普段と雰囲気が違うためか、ちょっと考えれば使わない方が良いなと判断できる言葉でも何気なく使ってしまうことがあります。
話の流れで出てしまう言葉なので、相手も気にせずお話しすることがほとんどですが、ふとした瞬間に思い出したり、挨拶の場でふさわしくない言葉を使った時には、印象に残っている事もあるでしょう。
また、普段は使っても悪い意味と取ることが無かったり、普通に使われる言葉でも葬儀の場では使わないなど、使っていけないと知らずに使われてしまう言葉も存在します。
ということで、今回は忌み言葉について紹介させていただきます。事前に知識を深めておくと良いですよ。
忌み言葉ってなに?どういう言葉を指すの?

忌み言葉とは、特定な場所や時で口にしてはならない言葉の事を言い、不吉な言葉や不幸が続くことを連想させる重ね言葉も当てはまります。
気にしすぎると、故人や家族へ本当に伝えたい言葉が出てこないという残念なことになりかねないのですが、代表の弔辞であったり、食事の前の献杯あいさつなど、あらかじめ用意できるあいさつ関係に関しては、特に気を付けるべきです。
では具体的にどういった言葉が忌み言葉と言われているのでしょうか?
「重ね重ね」「たびたび」「かえすがえすも」「ますます」「たび重なる」の、葬儀などの不幸ごとが重なることを連想される言葉です。
人は必ず亡くなるとはいえ、不幸ごとは多く起こることは良い事ではありませんよね?言葉を重ねることで、不幸ごとも重なって起こると表されてしまうのです。
これは女性のネックレスでも言えることで、2重を身に着けないことも、同じ意味で忌み嫌うからです。葬儀では言葉でもアクセサリーでも、重ねないように気を付けましょう。
「追って」「九」「四」「苦しい」などの故人のが亡くなったことによる、家族のつらい思いが表れた言葉や、苦しんだと連想させる言葉も避けた方が良いとされています。
また直接的である、「死ぬ」などもつかわず、「逝去」「亡くなる」を選んで使用すると、家族からみて丁寧な対応と感じるでしょう。
これは話言葉というよりは、特に弔電など文面のときに使うのではないでしょうか。家族に向かって「いつ死んだのですか?」なんて言う人はさすがにいないですものね。
葬儀で使える「お悔やみ言葉」を紹介!

葬儀の場で使う言葉としてふさわしい言葉は、悲しみやお悔やみを表現するうえで丁寧で死を連想させない言葉です。お悔やみの言葉は、家族に対してだけでなく受付でも使います。
「この度は誠にご愁傷さまでございます。」「謹んでお悔やみ申し上げます。」は受付でも使う一般的なお悔やみ言葉と言えます。
この他にも、「一般的なご冥福をお祈りいたします。」「ご自愛くださいませ。」といった丁寧で相手を思いやるお悔やみ言葉は最も葬儀に適した言葉でしょう。
また変換する言葉もしっかり使うと家族への配慮といえます。
- 「死ぬ」→「ご逝去」「亡くなる」「他界する」
- 「急死」→「突然の訃報」
- 「生きているうち」→「生前」「お元気なうちに」
これらの変換する言葉に関しては、弔電を送りたいという時に使う事の多い言葉になります。
定型文を送る場合は、すでに葬儀にあった言葉づかいで文章ができているものを選ぶので問題ないですが、フリーでお贈りする場合は、覚えておかないと失礼な弔電が出来上がることになります。
精進落としの前には、「献杯」の音頭をとります。これは決して「乾杯」ではありません。これは間違える人が多く、大きな声で「乾杯」と音頭を取る方がいるので気を付けたい言葉です。
献杯の音頭はわりと年長者が行う事が多いですが、残念ながら「乾杯」といった瞬間、常識のない人判定される事でしょう。
火葬場の待ち時間にお酒を飲みすぎて、酔っ払って…という人も中にはいますが、それはそれで問題ですけどね。
忌み言葉で失敗しないあいさつ例文の紹介

葬儀でのあいさつとは、喪主になった際の「喪主あいさつ」「出棺前あいさつ」、故人にお別れを述べる「弔辞」、精進落としの「食事前のあいさつ」、故人にお酒をささげる「献杯のあいさつ」などがあります。
喪主のあいさつ例文
喪主のあいさつは、会葬に来てくれた人への感謝の気持ちを述べます。出棺の前にあいさつすることから「出棺前あいさつ」とも言いますが、通夜時に「喪主あいさつ」、葬儀の出棺前に「出棺前あいさつ」と二回行う事もあるようです。
葬儀告別式の例文について紹介させていただきます。
「本日はご多用中なところ、ご会葬、ご焼香賜り誠にありがとうございます。おかげおもちまして葬儀並びに告別式を滞りなく終了させていただき、これより出棺の運びとなりました。生前は一方ならぬご厚情をあずかり、ここに最後のお見送りまでいただき故人もさぞ感謝いたしておるかと思います。なお残された遺族に対しても今後ともご指導、ご厚誼賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。」
このように、会葬に来て頂いたお礼+滞りなく式が終了した報告+これからの家族とのお付き合いのお願い、をあいさつ文に入れると良いでしょう。
弔辞の例文
弔辞は故人と自分の関係や故人とのエピソードによって、話す内容が変わります。共通して話す内容としては
「ご紹介いただきました○〇と申します。故人の○〇の代表としてお悔やみの言葉を申し上げさせていただきます。」
のように故人との関係と自分の名前を述べます。
次に「突然の訃報を受け気持ちの整理がつきません」など故人が亡くなり、自分がどのように感じているか、気持ちを伝えます。
次に「○〇さんは優しい人柄で、私に対して~」のように故人がどのような人っだったか、故人とあったエピソードを入れ込み話します。
後に「○〇さん安らかにお眠りください」などの言葉で締めます。
食事の前のあいさつ例文
食事の前のあいさつの例文は以下の通りです。
「本日はご会葬いただきありがとうございました。故人もこれで安らかな眠りにつけるかと思います。これも皆様方のお力添えのおかげです。故人にかわり厚く御礼申しあげます。なお粗酒粗肴ではございますが、お時間の許されます限りおくつろぎいただければ幸いです。本日はありがとうございます。」
来ていただいたお礼+食事を用意したのでゆっくり召し上がってほしい、ということを伝えてください。
献杯のあいさつ例文
献杯のあいさつの例文は以下の通りです。
「故人の○〇の○〇です。本日は故人の為にお集まりいただき、ありがとうございました。すべて無事終了し故人も安心しているかと思います。故人との思い出話をしながら過ごしていただければ幸いです。それではご唱和をお願いいたします。献杯」
献杯は乾杯とは違い、グラスを合わせず、故人の写真に体を向けグラスを捧げます。
まとめ
葬儀での言葉は普段何気なく使用している言葉で、普段の使い方としてもまったく悪い意味を持つわけではないため、なにも気にすることなく話をしていると気が付かないうちに、忌み言葉を使ってしまっていることはよくあります。
もしかしたら忌み言葉を自分が使い話していることに気が付かずに終わることもあるでしょう。
葬儀を行う家族は、故人が天寿を全うし亡くなったとしても、気持ちが落ち込み少しの事でも気になります。それは言葉一つとってもそうです。
家族に対しお悔やみの気持ちを伝えたいと思ったら、忌み言葉は把握しておくことがマナーでしょう。
またあいさつ文を考える際には、しっかりと伝えたいことを文章にし、その文に忌み言葉が当てはまっていないか確認して用意してください。
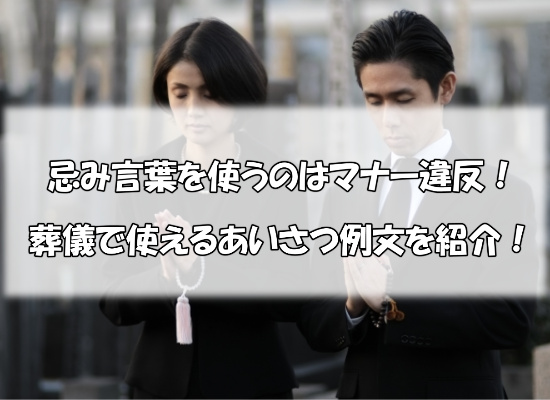

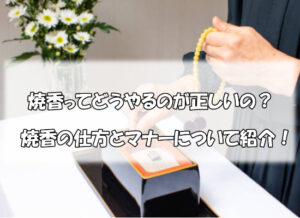
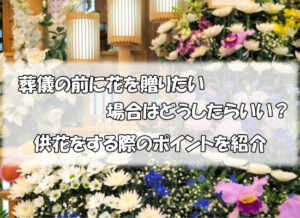
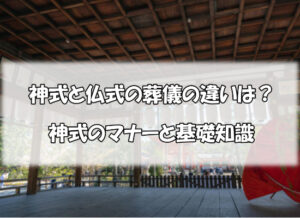
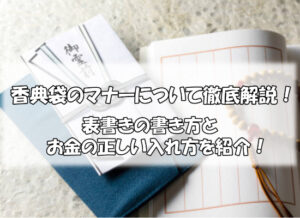
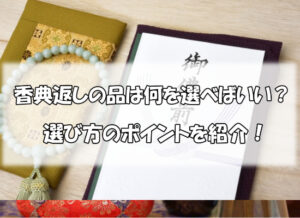
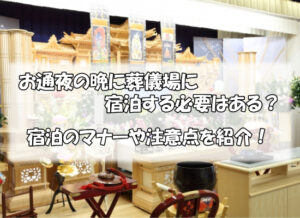
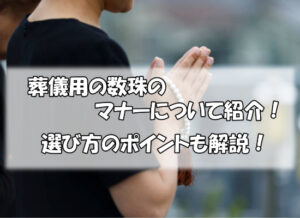
コメント