急な訃報により葬儀に行くことになった場合、注意したいことの一つに焼香のマナーがあります。
葬儀の場に慣れており、マナーをしっかりと把握している人は遺影写真に目をやり、神妙な面持ちをしたり、喪主を心配そうな表情で見つめています。
しかし、葬儀の場に慣れていない人は、自分の焼香の順番が来るまでキョロキョロ目が泳いでるなんてことがあります。
焼香が緊張する・不安だと考えている人の頭の中は想像できます。どこからあいさつをしたらいいのか、焼香は何回するのか…。
分かります!あの空気感独特ですよね。ということで、今回はそんな焼香のマナーについて紹介させていただきます。今まで悩んでいたという方もこれを読めば悩み解消間違いなしです!
葬儀の時にする焼香って何?

焼香というのは葬儀や法要に際して仏前や霊前に香を焚き、供養の心やお悔やみの気持ちを伝えることです。
焼香には立礼焼香(焼香台の前に立って焼香する)・回し焼香(香炉が順番に回ってくるので受け取り座ったまま焼香する)・座礼焼香(畳の場合など座った状態で焼香する)とやり方がありますが、今は立礼焼香を行う場合が多く見られます。
焼香の仕方について
焼香の順序は喪主から始め血縁の濃い順に行うとされています。焼香の仕方はまず焼香台のある仏前に進み本尊と遺影に黙礼をします。
次に、香をつまみ炭の入っている香炉へ1~3回移しいれ、合掌して退きます。この時念珠を持っている場合は左手に念珠をかけ右手で香をつまみます。
香をつまむ際は親指と人差し指と中指の3本の指でつまみます。大体の葬儀で喪主・親族・一般席に向かってお辞儀をしてから焼香をするかと思いますが、まず第一にあいさつするのは、故人やご本尊に対して(祭壇に向けて)になりますので気を付けましょう。
そののち喪主や親族は来ていただいた一般参列者に「参列いただきありがとうございます」という気持ちでお辞儀し、逆に一般参列者は喪主や親族に対し「お悔やみ申し上げます」という気持ちでお辞儀をします。
一般会葬者が一般会葬者の席に向け「お先に失礼します」という意味でしょうか、お辞儀をされる人がいますが、本来は必要ないと言えます。やってはいけないという事ではありませんが、やらなくてもいいでしょう。
多くの方が参列に来ている場合は、1回焼香やあいさつは喪主に対してだけと葬儀スタッフから指定がある場合がありますので指示に従うと良いでしょう。
焼香の時にやりがちな失敗

外国の方が日本で葬儀に参列した際、焼香が分からず前の人を真似しようと見ていたら、何やら器の中の物を掴んで口元に持って行っているように見え、自分の番になったので見様見真似で香を食べたなんてエピソードを話してるのをテレビで見たことがあります。
さすがに日本人で香を食べる人はいないとは思いますが、焼香での失敗エピソードって結構あるんです。
炭に手を入れてしまった
焼香は香の入った器と火のついた炭の入った器で分かれているのですが、香を炭に移すのを間違えて厚く熱せられた炭に手を入れてしまったなんてことがあるようです。
香と炭の間違いは煙が立っているのにもかかわらず間違える人がいます。指が炭ギリギリのとこまでいって「熱い!」と違いに気が付くようです。
これはお子さんにも多く見られるので、一緒に行かれる場合は親御さんが見てあげましょう。
お辞儀のタイミングが合わなかった
2人同時に焼香に進んだが、隣の人と喪主や一般会葬者へのお辞儀のタイミングが合わず、お互い向かい合ってお辞儀してしまったなんてこともあります。
これ結構多いですよね。向かい合ってお辞儀はまだ良い方で、隣の人と向かい合ってお辞儀したら距離が近すぎて頭をぶつけ注目の的なんて事も…。よく周りを見ましょうとしか言いようがありませんね。
焼香台に荷物をぶつけてしまう
カバンを置かずに焼香したらお辞儀した瞬間に焼香台にぶつけ大きな音を出してしまい恥ずかしい思いをしたというケースもあるようです。
仕事帰りで大きいカバンを持って参列される方も多くいますが、クロークや荷物置きがある場合は利用しましょう。
緊張していると思ってもみない行動をとってしまうことがあります。でも、人の行動って自分が思っているよりも他人は見てないんです。なぜかというと周りの人も自分でいっぱいいっぱいだからです。
なぜ失敗が目立つのかというと、それは失敗した後に笑ったり、あっ!と声を出すからです。ですので、失敗したとしても堂々としているというのが一番の対策です。
焼香は宗派によって作法が違う?

焼香をする際の作法って一つだと思っているかもしれませんが、実は宗派によって違いがあります。主な宗派の焼香作法は以下の通りです。
天台宗
回数については特に定めはありませんが1~3回の中で行うのが一般的です。
真言宗
回数は3回です。「仏・法・僧」へ3回ということです。
浄土宗
回数に定めはありませんが、「真心を込めて1回」もしくは「身を静めて1回・心を清めるのに1回の計2回」または「仏・法・僧へ3回」と1~3回の回数と言われています。
臨済宗
こちらの宗派は回数にはこだわりませんが通常1回とされています。
曹洞宗
こちらの宗派も回数にこだわりませんが通常2回とされています。
日蓮宗
回数は通常3回とされています。「仏・法・僧」の三宝供養、または「空・仮・中」の三諦にならうと言われています。
浄土真宗
本願寺派は1回、大谷派は2回とされています。
見ていただくと分かるように、焼香の回数は1~3回の間で定められており、焼香に意味を持っています。
回数にこだわらないという宗派もありますが、供養するという心を込めて焼香をするという事には変わりありません。何回やるのか考えず心御込めて焼香してください。
ここまでは仏式の宗派の焼香について紹介させていただいたので焼香は仏式のみと思われるかもしれませんが、実はキリスト教のカトリック教会やルーテル教会も焼香をされることがあります。
また葬儀に行けば必ず焼香をすると思っている人がほとんどかと思いますが、自分は信仰している宗教が違い焼香はできないという方、スタッフに一言説明すれば無理に案内されることはありませんので安心してください。
基本的にはその人の信仰している宗教や宗派を優先させることができます。式場に入らず黙とうでお悔やみの気持ちや供養の気持ちを表しても良いのです。
ただ、読経中の時間に間に合わず、他の一般の人と同じ焼香に間に合わなかった人が、後から一人案内され、親戚の注目を浴びてしまい嫌だから焼香を断る人がたまにいますが、その理由は完全にマナー違反です。
親戚に見られながら1人で焼香するのが気まずい気持ちはわかりますが、何をしに来たのかを今一度考え直した方がいいでしょう。
最後に
葬儀に参列することで重要なのは故人への供養や家族へのお悔やみの気持ちです。そのためにマナーを守るということが大切になりますので、失敗した・間違えたという事は気にせず慌てる必要はありません。
注目されるから焼香を拒否するのではなく、作法を多少間違えたとしても故人への思いを伝える方が何倍もマナーを守っていることになるのです。
厳密には上記のような焼香の回数など決まりがありますが、どの宗派も共通しているのは心を込めてということです。
急な訃報による葬儀で戸惑うこともあると思いますが、しっかりとマナーを守り個人への思いを伝えるようにしましょう。
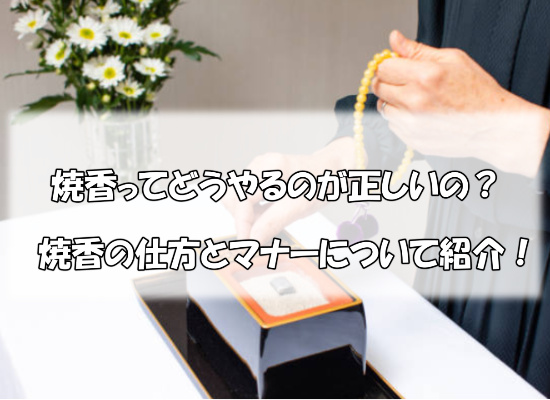


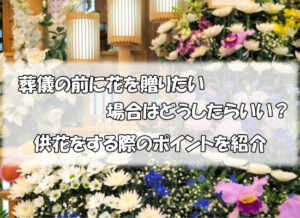
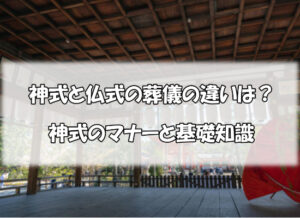
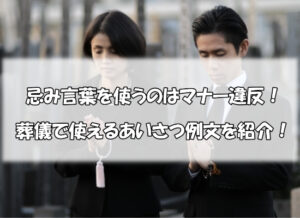
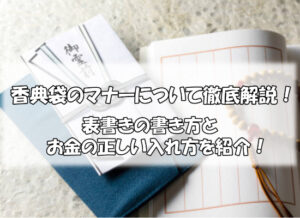
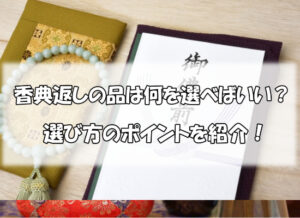
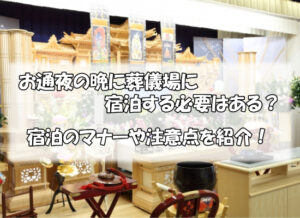
コメント