お葬式を終えたあとには、すぐに戸籍、年金、健康保険などの手続きをしなければなりません。
大切な家族を亡くされて身も心も疲れきっている状態でしょうが、期限が設けられている手続きがほとんどです。
そのため、悲しむ間もなく手続きに取り掛からなくてはなりません。
そこでここでは必ず最初に着手するべき、葬儀後に行う死亡後2週間以内が期限の手続きについてお知らせします。
尚、申請における諸手続きの期限や持ち物は変更になる場合がありますので、必ず事前に申請先にご確認ください。
手続き期限7日以内!必ず全員に必要な手続き

こちらの手続きは急いでしなければなりませんが、葬儀社が代理で届け出をしてくれる場合が多いです。ですので、自分でしなくてもよい可能性があります。
ただ、この手続きが終了していないと火葬することができないため、葬儀社に依頼している場合も必ず確認するようにしましょう。
もし、葬儀社へ依頼する場合には、届出人印鑑と代理人印鑑が必要です。
死亡届
死亡届というのは本人の死亡を証明する公的な証明書です。この届出が受理されると住民票に死亡が記載されます。
亡くなった病院などで死亡診断書が受けられるのでそれを役所に届け出ることで、死亡届を受け取ることができます。死亡届は24時間いつでも受付が可能です。
- 手続き期限:死亡を知ってから7日以内
- 手続き場所:死亡地か本籍地又は届出人の住所地いずれかの市区町村役場
- 持ち物:死亡診断書或いは検死検案書、届出人の印鑑
死体火葬許可申請
死体火葬許可申請書は申請直後に交付されます。この書類がないと火葬できないので注意して下さい。
- 手続き期限:死亡を知ってから7日以内
- 手続き場所:死亡地か本籍地又は届出人の住所地いずれかの市区町村役場
- 持ち物:死体火葬許可申請書
死亡届と火葬許可申請書は遺族年金や保険金などの請求時に必要になりますので、あらかじめ多めにコピーを取っておくことをお奨めします。
手続き期限14日以内! ~戸籍関連~

次は死亡後14日以内にしなければいけない戸籍関連の手続きについてです。
住民票の抹消届
住民票抹消届とは、死亡などで住民票から削除を依頼する手続きです。
こちらの手続きは、通常は死亡届の提出により特に手続きは不要です。
故人が3人以上の世帯の世帯主だった場合は世帯主変更届が必要です。
- 手続き期限:死亡から14日以内
- 手続き場所:市区町村役場 戸籍住民登録窓口
- 持ち物:届出人の印鑑、本人確認できる証明書類(免許証パスポート等)
世帯主変更届
故人が世帯主でありその人に2人以上の被扶養者がいる場合に住民異動届の手続きが必要となります。
- 手続き期限:死亡から14日以内
- 手続き場所:市区町村役場 戸籍住民登録窓口
- 持ち物:世帯主変更届(住民異動届)、届出人の印鑑、本人確認できる証明書類(免許証パスポート等)、国民保健被保険者証(加入していた場合)、委任状(世帯主以外の届出の場合)
手続き期限14日以内! ~年金関連~
次は死亡してから14日以内にしなければいけない年金関連の手続きです。
年金受給停止の申請
故人が年金を受給していた場合は年金に関する手続きが必要です。
また受給していた年金によって届出先、手続きの期限も異なるため注意が必要です。
- 提出期限:厚生年金は死亡後10日以内(国民年金は死亡後14日以内)
- 手続き場所:市区町村役場 戸籍住民登録窓口
- 条件:故人が年金を受給していた場合
- 持ち物:年金受給者死亡届、年金証書又は年金手帳、除籍謄本又は住民票除票、届出人の印鑑
手続きが遅れて、死亡後に年金が支払われるとその分を返還しなければいけなくなるので注意しましょう。
年金受給者死亡届の提出と同時に、未支給年金・保険給付請求書の提出も行います。
未支給年金の受取申請
未支給年金というのは、年金給付の受給権者が死亡した場合、その方に支給すべき年金であって、まだ支給されていないもののことを言います。
未支給分の年金を遺族が受け取れる制度ですので忘れずに提出しましょう。
- 手続き期限:年金受給停止申請と同時
- 手続き場所:それぞれの加入保険の手続き場所
- 持ち物:請求者の戸籍抄本と住民票(個人の除籍謄本や住民票除票に含まれている場合は不要)、請求者の印鑑、請求者名義の預金通帳
受給していた年金の種類や続柄によっては必要書類が異なる場合がありますので注意が必要です。
手続き期限14日以内! ~健康保険関連~
健康保険とは病気やケガの治療が必要な際、治療費の一部を保険者が負担する公的な医療保険制度です。
保険者とは職業によって異なり、会社員であれば勤務先が保険者となる健康保険、自営業であれば全国健康保険協会が保険者となる国民健康保険に加入しています。
日本では国民皆保険となっており、短時間のパート勤務の方でも国民健康保険に加入することになっています。
また主婦や、未成年のように収入がない場合でも家族の健康保険の扶養者として加入している場合がほとんどです。
よってどんな年代の方がなくなっても必ず手続きが必要になります。
国民健康保険の脱退
まず特に提出期限が明確に示されていて、国民の約30%が加入している国民健康保険の手続きについて紹介します。
- 提出期限:死亡から14日以内
- 手続き場所:市区町村役場 保険年金課
- 持ち物:国民健康保険資格喪失届、国民健康保険証
故人が74才以下で国民年金保険に加入している場合は、国民健康保険資格喪失届と国民健康保険証の返却を同時に行う必要があります。
故人が75才以上の場合には後期高齢者医療制度に加入しているので、そちらでの手続きを行います。
勤め先での健康保険の脱退
故人が74才以下で会社の健康保険に加入している場合には、基本的には故人が生前勤めていた会社が手続きを行ってくれますので、連絡を行いましょう。
故人の家族も故人の健康保険に加入していた場合は、家族全員の健康保険証も故人のものと共に返却します。
返却期限は特に決まりはありませんが、可能な限り速やかに行いましょう。
介護保険の脱退
介護保険の被保険者がなくなった場合は自動的に被保険者の資格が失われるわけではないんです。
資格喪失手続を行わなくてはいけません。ですので、速やかに手続きを行うようにしましょう。
- 提出期限:死亡日から14日以内
- 手続き場所:市区町村役場 福祉課などの窓口
- 持ち物:介護保険資格喪失届、介護保険証、保険料過誤状況届出書(還付金が発生する場合)
65才以上、または40才以上65才未満で要介護認定を場合に必要な手続きです。
最後に
身近な家族を亡くし、葬儀を終えたばかりでも遺族はたくさんの手続きに追われてしまいます。
ここに上げたものは直近の2週間で必ず行うべきものですが、思ったより多かったのではありませんか?
このあともライフラインや携帯電話の解約、生命保険の請求など、手続きは続きます。
全てを終えるのに1年かかり、やっと故人を偲ぶことができるようになったという声もあるほどです。
いざという時に慌ててしまい、手続きができない事は避けたいですから、特にお亡くなりになってからすぐに行わなければならない、上記の手続きについては事前に確認しておくといいでしょう。
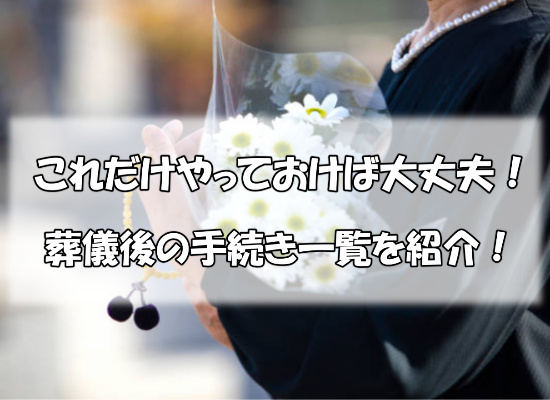


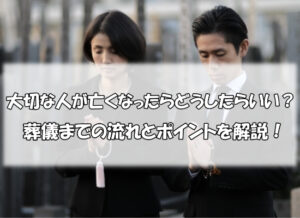
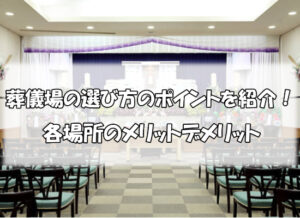
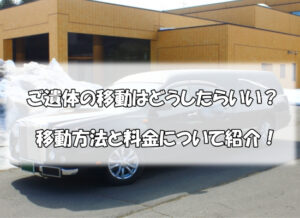
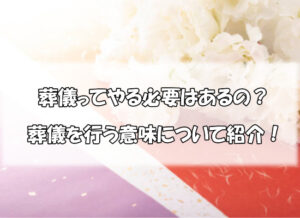
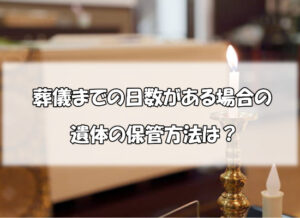
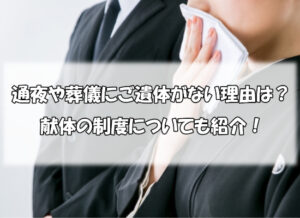
コメント