歳を取るにつれ葬儀に参列することは増えても、人生で自分が中心となり葬儀をとり行うことは多くないと思います。
多く経験して良い事では決してありません。しかし、いざ大切な親や最愛のパートナーがなくなった時、どうしていいかわからなくなり、葬儀社任せで気が付いたらやってあげたいと考えてた最後のお別れができなかったなんて後悔だけが残る結果になります。
葬儀は1度きりですので、何かあった場合も慌てずに済むよう今回は葬儀の流れと手順について紹介させていただきます。
大切な人が亡くなったらどうするの?

どこで亡くなるのかは人によって違います。病院で亡くなる方もいれば自宅で亡くなる人、どちらにも当てはまらない人もいるのです。
病院で亡くなった場合は、担当医より死亡の診断を受け看護師さんによる処置が行われます。その間に葬儀社へ連絡を入れるよう言われますので、葬儀をお願いする業者が決まっている方は、葬儀社へ亡くなったので故人を迎えに来てもらうよう連絡します。
どの葬儀社に連絡しても聞かれることがあり、その項目を決めておくとスムーズでしょう。
- 亡くなった方の名前
- どこに迎えに行くのか(病院の名前)
- 何時にお迎えに行ってよいか(処置は終わっているかの確認)
- どこに戻るか(自宅?葬儀社の霊安室?)
冷静な時に聞かれれば問題なく返答できる簡単な質問なのですが、大切な家族が亡くなり気が動転している状態だと答えることができなくなる人もいます。
自分の名前や故人の名前すら間違えて伝えてしまう人がいるくらいなので、慣れていない状況だと難しい事なのです。
葬儀社が決まっていない場合、病院で紹介してもらう事も可能です。霊安室や病室は特別な事情がない限り長時間(1日利用したいなど)使うことができないことが多いので気を付けてください。
では自宅で亡くなった場合はどうなるのでしょうか?それは亡くなった状況で少し違います。
病気で自宅療養中であったり、自宅で介護をされていて自宅で息を引きっとった場合、かかりつけ医が自宅にて死亡の診断をするので、診断を受けたのちに葬儀社へ連絡を入れます。
もし自ら命を絶たれたり突然亡くなり事件性があるかもしれない場合は警察の方が入ります。その場合は警察の方の確認と警察指定の専門医の診断が終了後葬儀社へ連絡することになります。
聞かれることは同じですが、病院ではなく自宅にいると答えが変わるので、自宅住所を聞かれるかと思います。
葬儀社と打ち合わせはどう進む?

故人を安置しお線香をあげたのち、葬儀の内容や日程の打ち合わせがスタートします。地域によって変わってきますが、確認していく内容としてはあげられるのは次の項目です。
- 喪主は誰がするか
- 式の形式はどうするか(仏式・神式・無宗教・その他宗教)
- 仏式・宗教は導師はどなたにお願いするのか(菩提寺や宗教の所属など)
- どこまでの人に声をかけるのか(家族葬や一般葬)
- 菩提寺がない場合、何宗でとり行いたいのか
喪主は基本的に配偶者や故人の長男や長女が行うことが多いですが、それは家族の事情で変わってくるかとは思います。また地域によって喪主と施主が別であることもあります。
菩提寺がある場合は亡くなった事を伝え、葬儀をとり行ううえで都合の良い日にちを確認します。日程の決定には、菩提寺の都合と式場の空きま日程と火葬場の空き日程が合い、初めて日程の確定になります。
日にちはしっかり確定してから来ていただく人にお知らせをしてください。先走りお知らせする方がいるが、混乱のもとになりますので気をつけください。祭壇・棺・骨壺・飾り方など細かい話も打ち合わせで決めていきます。
突然亡くなった時に家族が困るのが、遺影写真をどうするかです。今終活かぞくという言葉が認知され、エンディングノートと共に生前にプロのカメラマンに撮ってもらい用意している人が増えているのが遺影写真。
家族が自分の写真を選ぶのに困らないように、そして自分らしい姿の写真で作ってもらえるようにという思いでしょう。
通夜・葬儀・火葬の流れ

弔問者として通夜または葬儀に行く時と式を行う家族では、当たり前だが当日の動きも全く変わってくる。地域での違いや状況によって変わることを前提に通夜・葬儀・火葬の流れを書いていきたいと思います。
亡くなってからまで日にちがあかない場合、通夜当日に納棺を行うことは少なくない。納棺式は家族だけで執り行う場合もあれば近しい親戚や故人の友人が参加されることもあります。
棺の中に入れてあげたい物を用意するのだが、なかには故人に着せてあげたい物を用意する家族もいます。棺の中に入れられるものは原則燃えるもの。
金属などを入れると火葬した際溶けてお骨についてしまうなどの理由もあるそうです。また燃える物でも分厚い本などを入れてしますと、燃え切らず残ってしまうので、火葬場で断られ取り出すこともあるので確認したほうがいいでしょう。
家族は早めに式場へ行き、飾ってある供花の名前の確認や受付をされる方へのあいさつ、住職や導師へのあいさつなどを済ませ、通夜が開式されます。
葬儀当日は葬儀式を済ませ火葬場に行く又は火葬後に葬儀式と、やり方は地域や状況で変わってくるかと思います。また初七日までこの日に終わらせてしまう事も最近は多いです。
全て済んだのち精進落としを行い終了となりますが、この精進落としも火葬場の待ち時間を使い済ませるやり方も増えており、少しづつ簡略化されているのが現状です。
大事な葬儀を簡略化するなんてと思われる人もいるかもしれないが、遠方から来てくれる親戚の時間をあまり多く取らせたくない、その日のうちに帰らせてあげたい、高齢化が進み長時間では体に負担がかかってしまうなどの配慮なども含まれているようです。
最後に
大切な家族との突然の別れで心を痛めてる中、家族はゆっくりしている間もなく葬儀のための準備をしなくてはいけません。
しかし何もわからずその場の流れに任せると後悔することもあります。故人のために最後に「何か」してあげることができる場になるので、あらかじめこの「何か」を考えておくといいかもしれませんね。
また写真など準備できることは元気なうちにやっておく、それこそ今話題になっている終活は大切なことで、葬儀について話し合う事や用意することは不謹慎なことではないのです。
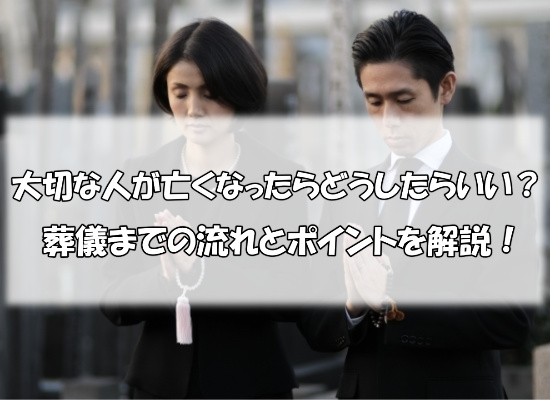


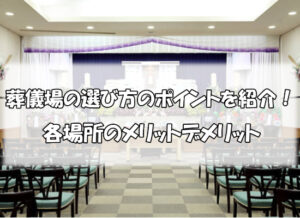
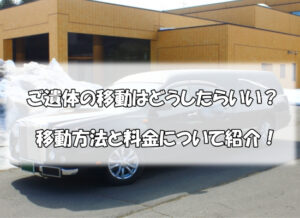
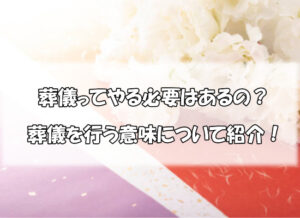
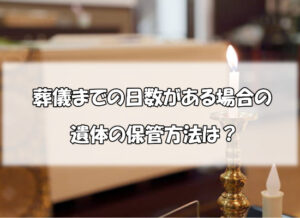
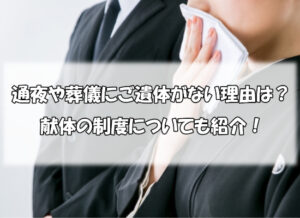
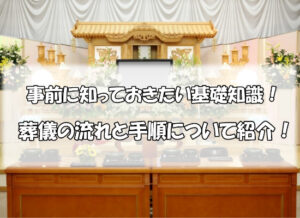
コメント