人が逝去すると当たり前のように、通夜と葬儀を行いますが、ふと思ったことはないですか?
「通夜と葬儀ってなんで必要なの?」「やらなくてはいけないことなの?」と…。
きっと自分より目上の人に聞いても、「弔いの為に」とか「やるのがあたりまえだから」という答えが聞こえてくるのではないでしょうか。
正直なところ、自分が逝去して弔ってもらったことがあるわけがないのですから、逝去した人が、通夜と葬儀をやってもらうと何が起こるのかなんてわかるはずもありません。
今は通夜や葬儀をやらず火葬のみで終わらせる身内や、通夜をやらず告別式のみで終わらせる身内も増加してきているため、通夜と葬儀を行う事は必須なのではないかと感じている人は増えているのでしょう。
もちろん金銭面の関係で火葬のみを選ぶ身内もいます。故人を思ってとりおこなう事が大事ですので、火葬式では故人の弔いにならない、故人が報われないなんてことはないと思いますが、意味があるから、昔から行われてきているはずです。
では通夜と葬儀をやる意味とはなんでしょう。宗派などによって違いはあるのでしょうが、ここでは一般的な仏式と神式で見ていきたいと思います。
通夜と葬儀をするのが当たり前ではなくなっている?

昔から通夜と葬儀の2日間故人の為にとりおこなうのが一般的で、執り行う場所の変化はあるものの、故人の弔いのために身内は準備し執り行ってきました。
しかし、だんだんと近所との付き合いがなくなったり、高齢化が進み故人の友人を呼ぶことが難しくなってきたりと、規模の小さくした式を希望する家族が増加してきました。
さらに喪主の会社関係や遠縁の親戚を呼ぶのをやめたりと、家族葬と言われる形式が注目され、昨今では葬儀を考えたときに家族葬が一番に浮かぶ人も少なくありません。
また、身内だけしか来ないから通夜はやらずに葬儀のみの1日葬、特に信仰心はないからと火葬式など、簡略化されたやり方が主流のように扱われることもあります。
では何気なく読んでいる、「通夜」「葬儀」「告別式」というのはどういう意味があるのでしょうか。
通夜について
通夜は身内や親族など近しい人たちが集まり、夜通し故人とへの思いを語らい、弔いをとりおこなわれたことから「通夜」と呼ばれます。
現在では式場で行われることもあり、清めの食事も含め3時間程度で終了します。また通夜に友人関係や仕事関係の人たちが集まるようになりました。
葬儀・告別式について
葬儀は家族や親戚と故人とゆかりある人たちが集まり、各宗教の導師によって弔いのため逝去する世界への葬送の儀礼をおこなう事から「葬儀」と呼ばれます。
告別式は身内や親族と故人とゆかりのある人たちが、故人に最後のお別れの思いを告げる事から「告別式」と呼ばれます。
葬儀と告別式は一緒にとり行う事が一般的になっているため、明確な違いが分からないもしくは同じ物思われていることも多いでしょう。
そのため葬儀・告別式ではなく合わせて「葬式」と呼ばれることも一般的になってきています。
仏式の読経や神式の儀式は通夜と葬儀で違う事を行うの?

仏式や神式など式の形式は様々で、身内がどの宗教を選択するかによって、変わってきます。
しかし、通夜と葬儀の2日間とりおこなう事は同じですし、それぞれおこなう趣旨は違います。
では現に通夜と葬儀ではどういった儀礼としておこなわれるのでしょう。
仏式の場合
仏式では「読経」と言って声に出してお経を読みます。通夜は故人に対し、「残した家族を案ずることなく浄土へと行ってください」という、気持ちを読経で説いています。
葬儀では引導を渡し、故人を来世へ旅立つことができるよう仏道へ導きます。読経の時間は約20分~40分くらいですが、長い住職だと1時間という事もあります。
参列者は通夜・葬儀共に、その中で焼香という形で故人への気持ちを伝えます。仏式では宗派が多く存在するため、全てに当てはまるとは言えません。
たとえば浄土真宗は即身成仏の概念ですので、仏道へ送り出すのではなく、あの世へのお迎えが来るなど違いはあるのです。しかし故人をしのぶ意向や内容であることは変わりありません。
神式の場合
神式では通夜を「通夜祭」と呼びます。この通夜祭では主に遷霊の儀と呼ばれる、故人の霊を霊璽(仏式でいう位牌)に移す儀礼「みたまうつし」が行われます。
本来は夜間に行われるのですが、今は通夜際でやる場合、室内の明かりを消し対応するように変わりました。
葬儀にあたる「葬場祭」では、祝詞で故人についてを語り、御霊のご平安を祈ります。参列者は通夜祭・葬場祭共に、宮司によりおお祓いで祓い清め、玉串奉奠にて故人への気持ちを伝えます。
火葬式と無宗教葬を選んだ場合、式として意味はないの?

火葬式は「直葬」と呼ばれることもありますが、通夜や葬儀のような宗教儀礼はとり行いません。納棺式と最後のお別れのみをおこない、そのまま火葬場へと出発します。
中には病院や施設からそのまま火葬場に行き、その日のうちに火葬を終えることができると勘違いされている方がいますが、基本的には一度家や霊安室に安置が必要です。
それは逝去してから24時間経過しなければ、火葬ができないという決まりがある事が理由です。
ただ、例外はあります。それは国が指定している感染症で逝去された場合です。最近ではコロナウイルスがその一つです。指定された感染症で逝去した場合は24時間以内にそのまま火葬場へ行き火葬されます。
葬儀をおこなわないため、負担額が抑えられることで火葬式を選ぶという身内もいます。
しかし、宗教儀礼が行われませんので、成仏するため・弔いという意味で考えてしまうと当てはまるとは言えません。
では、葬儀をやる意味はないのでしょうか?
そんなことはありません。気持ちが込っているのであれば、身内が故人を思い、お別れをするという趣旨で言えばやる意味はあります。
では無宗教葬ではどうでしょう?無宗教葬は仏式や神式など宗教は無く、生演奏で音楽を流す、故人とのスライド写真を流し語らうなど、故人とのお別れの為に身内が何をしたいのか考えとりおこないます。
無宗教葬も火葬式と同じで、成仏するためや供養のためという意味では当てはまらないと言え、やはり身内が故人とお別れをするという所に重点が置かれた式と言えるでしょう。
もちろんやる意味がないということはありません。宗教儀礼には当てはまらないという事です。
最後に
ただ人を呼ぶのは大変だから、葬儀に出せないという理由で、火葬式や1日葬を選ぶ身内がいます。
その反面、どうしても通夜と葬儀をおこなうことができない理由があり、火葬式や1日葬を選ぶという身内もいます。どちらの身内も、選んだやり方は間違えではないのです。
しかし大きく違う事があります。それは故人に対しての気持ちがあるかという事なのです。
もちろん通夜は通夜をやる意味が、葬儀は葬儀をやる意味があるのだから、2日間弔いをしてもらう事が一番ではあります。
しかしそれが叶わない状況というのはあり、弔いを優先できないこともあるのが現実です。
コロナウイルスの影響を受けている今、密を避けるため家族葬で行う身内はさらに増加しています。
通夜と葬儀の意味のある作法をおこないつつ、新たな葬儀のとりおこない方を確立する時が来ているのかもしれません。
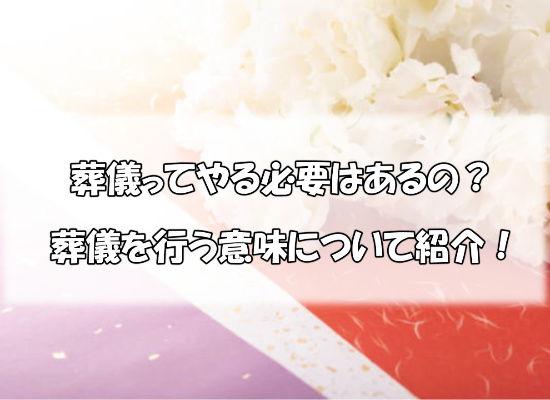


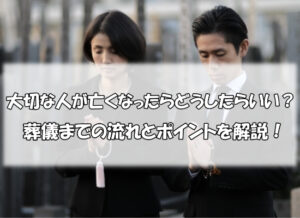
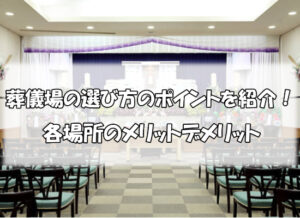
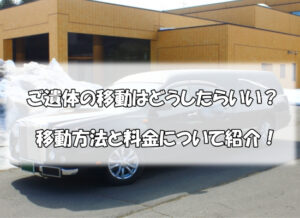
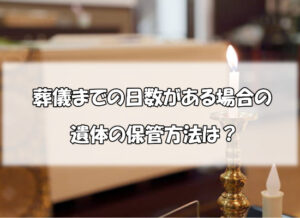
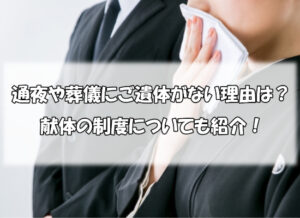
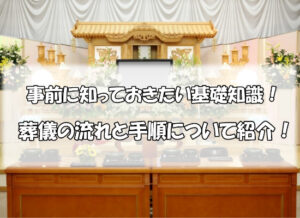
コメント