人が亡くなるとき、最後の時をどこで迎えるかは人によって違います。もし、病院や施設の場合、亡くなってからも長時間その場で安置させてもらう事はできません。
ですのですぐにご遺体を移動させる必要があります。その時の移動手段は、必然的に車になるでしょう。故人を移動させる専用の車である寝台車を手配し、移動させるのが一般的です。
しかし、その他にも故人を移動させる方法はあります。ただ、その方法には注意点もあるので気を付けなくてはいけません。
では寝台車を手配するにはどうしたらいいのか?そもそも寝台車とは普通の車と何が違い、寝台車で移動させるメリットとはなにかをお伝えさせていただきます。
また、寝台車以外で移動させる方法とはなにか?またその時のメリットとデメリットについても紹介させていただきます。
遺体の搬送は何でする?寝台車をどこにお願いするの?

病院や施設で家族が亡くなり故人を自宅または葬儀屋さんの霊安室に移動させるとなった場合、どのような手段で移動するか知っていますか?
詳しくは知らないけれど、多分葬儀屋さんや病院、施設で手配した車で移動するんだろうなって考える方がほとんどだと思います。
実際にその方法で間違いありません。ただ、意外と知られていないのが「寝台車」を手配した時の料金です。後で請求されてビックリしたなんてことにならないように注意しておきましょう。
まず、寝台車というのは故人を寝かせた状態で車に乗せることができ、長距離であっても無理な体勢をすることなく移動できる車の事をいいます。
また棺に入った状態でも乗せることが可能であるのですが、棺に入っていない場合はストレッチャーを使用します。救急車も寝台車の種類の中の一つです。
この寝台車は、亡くなった際に葬儀屋さんへ依頼の電話をすることで寝台車の手配をしてもらう事が可能です。
寝台車は走った距離で金額が変わります。葬儀屋さんの中には依頼をしてくれたお客さんに、「〇キロまで無料搬送します」まどと、うたっていることもあります。
料金の目安ですが、タクシーで移動した場合の10倍程度の金額となります。もし、病院から10㎞程度搬送してもらった場合、4万円程度かかる計算になります。
深夜や早朝の場合は追加料金が発生する場合もあります。病院を通して葬儀屋さんに頼むことで、無料搬送してもらえることもあるのでぜひ一度調べてみてください。
寝台車には車の種類があり、霊柩車と同じような黒のバン型であったり、シルバーや白や黒などのミニバンです。ほとんどの方が寝台車の形を指定することはありません。
しかし、中には家に連れて帰りたいけど亡くなったという事を近所に知られたくないという相談もあり、外からは普通の車と変わらないミニバンでと言われることもあります。
葬儀屋さんもネクタイを黒からカラーの物に変えたり、ジャケットを脱いで対応したりと、お客さんの要望にこたえる形を取ることが可能です。
遺体の移動に自家用車が使えるって本当?注意点は?

故人を運ぶことができる車は寝台車や霊柩車など、専用の車だけと思っている人は多いのではないでしょうか?
それはほとんどの人が、寝台車などを手配して利用するのが一般的になっており、それ以外を見たことが無いという理由でしょう。
実は故人の移動は自家用車でも可能です。病院から発行される死亡診断書を持って自家用車で運ぶのであれば法律違反ではないのです。
しかし、自家用車で運ぶ時の事を考えてください。亡くなった人を座席に座らせ、シートベルト着用で移動は難しいと言えます。
寝台車のように、寝かせて運ぶことは可能ですか?車の揺れで移動してしまう事が無いように、支えはありますか?もしくは誰か抑えて目的地まで行ける人はいますか?
このように自家用車で運ぶのには短距離であっても準備や工夫が必要になります。ましてや長距離となったらさらに大変でしょう。
様々なリスクを考えた場合、寝台車で移動することの方がはるかに安全で安心と感じるのではないでしょうか。
逆に葬儀屋さんが自家用車でもいいですよと、提案することもあります。それは、故人が赤ちゃんや小さい子供の場合です。
親御さんからしたら、小さい子供を寝台車に一人乗せるより、ご自身で抱いていたいと感じることでしょう。ご両親が抱いて移動することのできる大きさの子供であれば車の揺れを心配することもありません。
霊柩車も自家用車で行きたいと希望される人もいます。葬儀屋さんに希望を伝えてみると、いいかもしれません。
遺体の移動に必要な死亡診断書とはなに?

遺体を移動する際には死亡診断書が必要になり、これを持たないまま移動させると違反になります。というより事件性があるとして事情聴取される可能性がありますので、気を付けなくてはいけません。
ではその死亡診断書とは何でしょう?
死亡診断書は故人が亡くなったと診断をした医師によって書かれた亡くなったという証明書になります。
故人の名前や生年月日など故人の情報に加え、亡くなった場所や日にち・病名など亡くなった状況などが記載されています。
事故や自殺など警察が介入しての出されるものは、死亡診断書ではなく死体検案書が出されます。死亡診断書や死体検案書の見開き逆側が死亡届けになっています。
死亡届とは故人の名前や住所や本籍などを家族が記入し、死亡してから7日以内に市区町村の役場に提出をするものです。
この死亡届を役場に提出すると死亡の手続きが行われ火葬をする許可がおります。火葬許可書という書類です。この火葬許可書がないと火葬場で火葬を行う事ができません。
火葬許可書は火葬を行う日に火葬場に提出を行います。火葬が終了すると火葬場より火葬の証明と埋葬許可書として家族の手元に戻り、これは納骨を行う際に必要な書類になります。再発行はされませんので納骨まで大切に保管する必要があります。
死亡診断書や死体検案書は役場に提出すると取り消すことも書類を戻してもらう事もできません。葬儀の後の手続きで診断書の提出を求められることがあるため、コピーを取っておくと良いでしょう。
最後に
ご遺体を移動する際に葬儀屋さんや病院に手配してもらった寝台車や霊柩車を使用するケースがほとんどだと思いますが、移動させてもらうのには安いとは言えない金額がかかります。
ですので、中には利用しないで移動したいと考える人もいるでしょう。もちろん自家用車移動することも可能とは書きましたが、移動でのデメリットを把握して決めることは大切です。
長時間の移動になればなるほど故人の体への負担は大きくなり、腐敗が進んだり、損傷が目立ってしまう事もありますので、寝台車を使用するのはそういった面でも、優れているといえます。
死亡診断書の役場での手続きや火葬場への提出は葬儀屋さんが行ってくれることが多くなっていますが、家族が行う場合は不備がないように気を付けなくてはいけません。
また埋葬許可書の扱いに関しても、必ず必要な書類ですので失くさないように気を付けましょう。
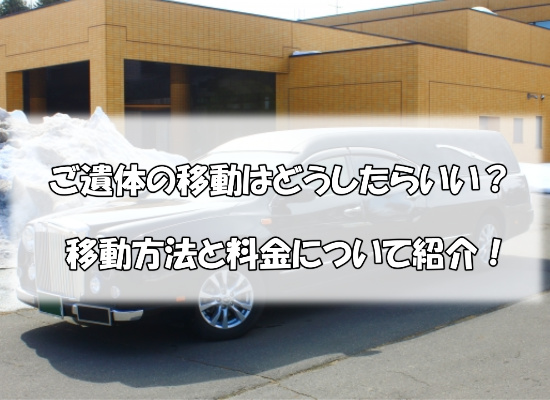


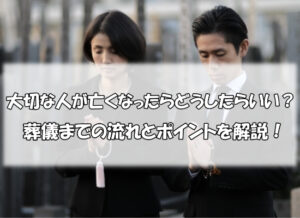
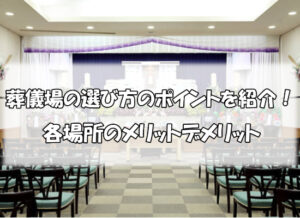
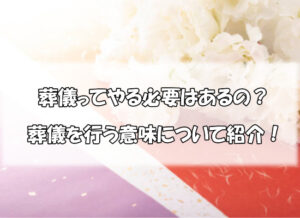
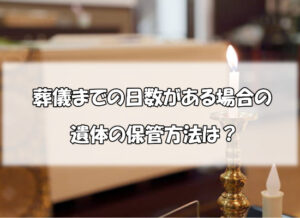
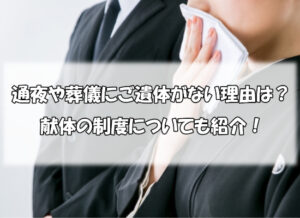
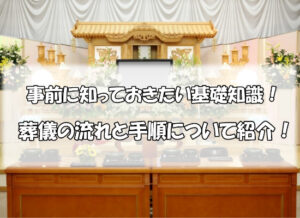
コメント