お別れの式であるお通夜や葬儀、告別式に参列することは、突然決まることが多いです。
喪服や袱紗などを慌てて揃えることも大変ですが、女性が案外と困ってしまうのがバックです。
選び方を誤ってしまうと周囲から浮いてしまうだけでなく、気づかないうちにマナー違反を犯してしまっているかもしれません。
黒色ならばなんでも大丈夫だろうと適当に選ぶ事は、故人やご遺族への配慮が足りないと思われてしまう可能性があります。
葬儀に参列する身内の方や周囲の方に失礼のないよう、葬儀の場にふさわしいバックを選ぶようにしましょう。
ということで、今回は葬儀用バックの選び方について紹介させていただきます。
葬儀用バックの選び方のポイント

葬儀用のバックは日常使いとは違い、年に数十回も使うものではないので、一度購入したのち何度も買い換えるものではありません。
季節を問わず、年代を選ばず、長く使えるようなシンプルなデザインのものを選ぶようにしたらよいでしょう。
型崩れしにくい、しっかりした作りのものを選ぶのも大切です。
葬儀の場では、葬儀場の床に置いたり、場合によっては、地面に直接置くような場面もあります。
ですので、バックの底に鋲の打ってあるデザインの物の方が汚れを防ぐ上でも、丈夫さの点でも安心です。
フォーマル用として冠婚葬祭いずれの場面でも使用できるようなバックは多種類販売されていますが、慶事寄りにデザインされているものもありますので注意しましょう。
葬儀は故人を弔うものですので、おしゃれ心や遊び心、ファッション性は必要ありません。
ブランドのロゴなども控えめにし、シンプルで簡素なものを選ぶことが重要です。
葬儀用バックにふさわしい形、素材、装飾を紹介

葬儀に参列する際に持っていくバックは黒色の布製で光沢のない、目立つ装飾金具がないものが基本です。
和装の場合も、黒色布製のクラッチバックがフォーマルとされています。どんなバックを選べばいいのか紹介させていただきます。
素材
素材としては、布製が正式でフォーマルさを感じさせます。華やかな模様や柄の入っていない、無地のものを選びます。
革を使用したものは殺生を思い起こさせるということから避けるようにします。
特に爬虫類などの型押しのものや毛皮やバックスキンのものは選んではいけません。
最近では革製や合成皮革製であってもツヤ消しされた控えめなものならばマナー違反でないとされることもあるそうですが、基本的には避けたほうが無難です。
人の目線が集まるような悪い目立ち方をしないことが重要ですので、可能な限り革製品は控えましょう。
大きさと形
大きさや形は、腕にかけられるタイプのハンドバックがお勧めで、小ぶりのものが主流です。
必ず持っていくべきものだけが入るようなサイズにしておきましょう。
たとえ小さめであっても、ショルダーバックやリュックサック、トートバックはカジュアル感が強くなってしまうので適しません。
バックの装飾
装飾としては、光に反射し輝くものはふさわしくないとされています。
バックの内側裏地や金具にも注意をします。開閉用のファスナーやスナップ、バック底の鋲などは必要以上にきらびやかなものでなければ、バックの性能上必要なものであるので、マナー違反にはなりません。
ただ、バックの留め具のところに装飾要素の強い金具が付いているものや、大きなブランドのロゴが付いているようなもの、バックを開けた時に見える裏地が非常に派手なものは避けましょう。
バックは開くことも少ないのであまり人目につくこともないかもしれませんが、葬儀の場にそぐわないものは意識して排除していきましょう。
男性は葬儀用のバックは必要なの?
葬儀に参列する際には、女性は必ずバックを持っていますが、男性はどうしたらいいでしょう。
マナーとして、男性はフォーマルの場面ではカバンを持たないことが基本です。
それは慶事弔事に関わりませんので、お葬式に参列する際にも基本的に手は空けておきます。
ハンカチや数珠、袱紗に包んだ香典などの持ち物は全てポケットにいれた状態で手には何も持っていない状態がフォーマルとされています。
香典などは上着の内ポケットに入れるのが一般的ですが、荷物が多く胸が膨らんでしまうと見栄えが悪いので注意しましょう。
どうしてもポケットに入りきらないような時には、黒い小さなセカンドバックのようなものを選びます。
黒色でないグレーやネイビーは避けたほうが無難ですし、革製の物も女性のマナーと同様、革は殺生を意味するものですので葬儀にはふさわしくありません。
遠方へ出掛けて参列される場合や、急なお葬式に参列される場合、リュックやボストンバックなどを持っていく事になるかもしれませんが、大きなカバンは受付などに預けるなどして、会場へは持って入らないようにしましょう。
葬儀の際には、荷物は自分の膝の上や椅子の下、壁と背中の間などの小さなスペースのみに置けるようなサイズを選びます。
葬儀用バックに入れておくべきものは何がある?
葬儀に行く際に必ず準備するものとして香典、袱紗(ふくさ)、数珠があります。香典の不祝儀は袱紗(ふくさ)という布に包んで持参します。
袱紗(ふくさ)

葬儀にふさわしい袱紗の色は、弔事用の黒、グレー、ネイビー、緑などの寒色系の色のものがいいとされています。
慶事弔事双方に利用できるとされている色は紫色で、両用の袱紗も様々なデザインのものが市販されています。
同じ袱紗だからといって結婚式に持参する慶事用のピンクやオレンジ色のものを流用する事はやめましょう。
数珠
数珠はお焼香の際に手に提げて使います。数珠は宗教宗派によって使用する物が異なる場合があるので、迷うならば宗教宗派を問わない略式数珠を選んでおくとよいでしょう。
葬儀では各人それぞれに数珠を用意して、お焼香の場で貸し借りをするのは良くない事であり、マナー違反とされているので注意します。
袱紗や数珠に関しても、訃報とともに突然に必要になるものですので、社会人になったら一式準備しておくのが安心です。
財布
必ず持参する三点以外のバックの中の持ち物について気をつけたいものとして、お財布とハンカチがあります。
まず財布ですが、あまりに派手な色のものは避けたほうがいいでしょう。
黒やグレーネイビーといった色味のものを葬儀用に用意しておくか、葬儀の場で財布を出すことのないよう意識しておく必要があります。
ハンカチ
ハンカチは白色か黒色の単色無地、または同色レースのもの、同色で地味な刺繍がされているもの等がふさわしいです。
本来は白色がフォーマルで正式なものであるとされていましたが、最近では喪服に合わせてハンカチも黒色でも正式であるとされています。
弔事用として男性用も女性用も黒色のハンカチが多種類あり、購入することができます。
最後に
葬儀に参列する際、喪服にふさわしいバックについて紹介させていただきました。
葬儀用のバックを選ぶ際に大切なことは、故人や遺族に失礼にならないよう、心配りをした上でバックを選ぶということです。
バックは黒ならばなんでもいいだろうと思いがちかもしれませんが、それではお亡くなりになられた方への尊敬や偲ぶ心を表すことが出来ません。
選ぶバックひとつであなたの故人への思いが表現されているのだと考えましょう。訃報は突然やって来ます。
若いからと思い準備をしていないと間に合わないこともあるでしょう。年代に関わらず日頃から備えておくことが必要です。
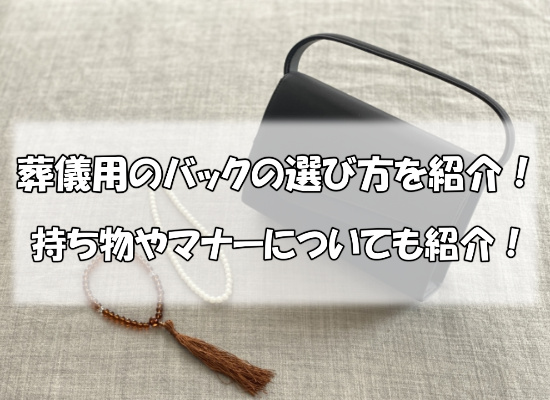


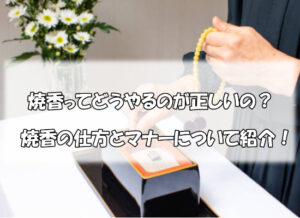
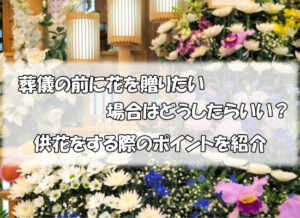
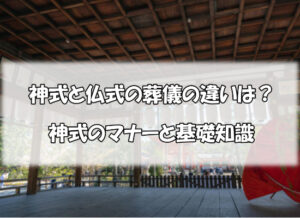
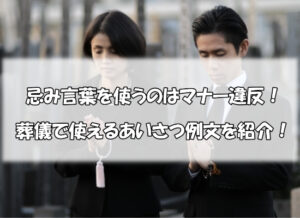
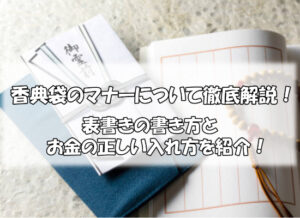
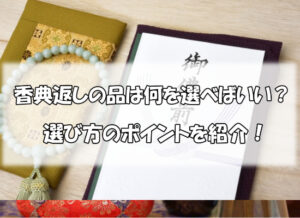
コメント