通夜や葬儀に行ったらご遺体はなく、お骨が祭壇に飾られていてびっくりしたという事はありませんか?
地域によっては骨葬を行う事もありますが、それは葬儀での話です。通夜にはご遺体が棺に入り、来てくれた人は拝顔することが可能です。
来てくれた人は故人と最後にお別れしたい、一目顔を見たいと思い出向くことでしょう。
しかし会いに行った先ですでお骨になった後だったらビックリするし、理由がわからずモヤモヤすることにもなるのではないでしょうか?
骨葬を選ぶ理由としては、地域のやり方という理由以外に、先に火葬するのには様々な理由があります。
その理由によっては、家族にとって大変つらかったり、強い悲しみを抱いている可能性があります。
会葬者に触れてほしくないと感じていることもありますので、親しい中であっても深く聞かない方が良い場合もありますので注意しましょう。
葬儀の前に火葬するのには理由がある?

葬儀の前に火葬するのには理由があります。ではその理由とはなんでしょう?それには以下の理由が考えられます。
- 家族での葬儀(密葬)を済ませ、本葬やお別れ会である
- 拝顔ができる状況にない
- 海外で亡くなった
- 国の指定する感染症で亡くなった
- 葬儀までの日程が空いてしまった
- 火葬場の空き状況の問題で先に火葬するという選択をした
家族での葬儀(密葬)を済ませ、本葬やお別れ会である
密葬とは本当に近しい人、家族や親戚のみで通夜や葬儀・火葬まで終わらせる事で、その後改めて故人とのつながりのある人を呼び本葬やお別れ会を行います。
有名人の方が亡くなるとこのような形を取ることが多く、テレビでお骨が飾られた祭壇が公開されることもあるかと思います。
拝顔ができる状況にない
拝顔のできる状況ではないというのは、亡くなり方が病死などではなく、事故など顔に大きく傷が残ってしまった事が理由と言えます。
最後に拝顔した時の顔でなく、元気な時の顔で思い出してほしいという家族の願いも含まれるでしょう。
海外で亡くなった
亡くなるのが国内とは限りません。旅行や仕事で海外に行っている際に亡くなってしまう事もあります。
その際は長距離の移動となり費用は高額となるため火葬を済ませてから日本に戻ることも少なくありません。
その場合は家族と共に海外に移住しているなどの理由が無い限り、日本での骨葬になります。
国の指定する感染症で亡くなった
国の指定する感染症の場合、亡くなったらすぐに火葬をされます。ウイルスが外に漏れださないように、感染が広がらないようにという理由です。
家族でさえも最後の拝顔を許されることはありません。新型コロナウイルスが当てはまります。
有名人もコロナウイルスによって亡くなり、家族の拝顔も叶わずお骨で帰ってきた姿は印象的だったはずです。
葬儀までの日程が空いてしまった
日程や火葬場の空き状況の関係では、葬儀の日程は菩提寺など司式者の予定と、火葬場や式場の空き状況と家族の予定を合わせ、葬儀の日程の確定になります。
菩提寺の場合特に住職がお忙しい場合もあり、近い日にちが難しい事もあります。それは住職は葬儀だけを行っているわけではなく、法事などお寺の仕事は様々。また檀家さんの数多くいますので、予定が重なることもあります。
火葬場の空き状況の問題で先に火葬するという選択をした
火葬場に関しても、時間ごとに何枠までと予約の制限もあり、亡くなる人が多くいる季節、特に火葬場のお休みが入ってしまう年末年始は、予約が取りづらくなります。
時には時間も選択ができないこともあるのです。このため、早い時間の火葬になってしまったり、日にちをずらす必要がでてきます。
日にちが延びたり、火葬の時間があまりにも早い場合は、先に火葬を済ませ、その後葬儀を行う事を選択することを進められるのです。
しかし、注意しなくてはいけないのは、菩提寺である場合は、先に火葬をすることを住職に相談しなくてはいけません。
もしも、許可を得られなかった場合は、エンバーミングをし、日にちがあいても故人の腐敗が進まないように処置を施すなど、別の方法を考える必要があると言えます。
先に火葬する場合と後にする場合とで違いはある?

通夜や葬儀よりも先に火葬する場合は通常の流れと何も変わることはありません。しかし、葬儀の前に火葬を行う場合は流れが変わります。
ただ、通夜までの流れは変わりません。葬儀ではまず家族や親せきが集まり火葬場へ行きます。その後、火葬を終わらせたのち式場へと戻り、お骨を祭壇に安置し葬儀が始まります。葬儀の後は精進落としの食事を行い終了です。
葬儀の前に火葬を行う事のメリット
先に火葬を行う事のメリットは、日数が伸びてしまった時に故人の状態を心配しなくて済む事や、大規模なお別れ会を考えている際に会場の選択の幅を広げること可能となります。
ホテルなどはご遺体の安置の受け入れを行わないことがほとんどなのです。また火葬が先になることで、火葬の時間が一番早い時間になったとしても、来てくださる人への負担の軽減をすることができます。
地域によって違いますが、例でいうと、1番早い火葬の時間は9時、その火葬に合わせて葬儀を行うと、7時からの開式となり、集合時間はさらに早い時間となります。
このように考えると、火葬を先にやらなくては来てくださる一般会葬者だけでなく、親戚ですら集合は難しくなってくるのではないでしょうか。
葬儀の前に火葬を行う事のデメリット
先に火葬をすることによるデメリットは骨葬になることによって、故人に拝顔することが叶わなくなるという事です。
これは一番のデメリットであると言え、感染症の問題など国が決めたこと以外の理由の場合、火葬を先に行わなくてはいけない理由を特に身内に対して明確に説明しておく必要がある可能性もあります。
骨葬をおこなわない地域にお住いの親戚にとって、拝顔ができずにお別れという事は、理解ができず揉め事につながるといえます。
遺体もお骨もない葬儀もある?献体とは何をするの?

葬儀の際にご遺体のない骨葬を行うにはもう一つ理由があります。その理由は献体です。
しかし、この理由は家族によっては故人を式場に安置して一般的な葬儀を行うパターン、骨葬をおこなうパターン、遺体もお骨もなく葬儀が行うパターンと、選択によってやり方が変わってくるので、献体を行うと必ず葬儀はこうやると言えません。
献体ってなに?
献体とは亡くなった方が日本の医療の発展のため、自分の体を医大などに提供し、解剖などに使われることをいいます。
この献体のおかげで未来の医者を生み、病気を治す可能性を広げることになります。献体をする場合、亡くなってから48時間以内に病院へ遺体を受け渡さなくていけなくなります。
そのため、故人と拝顔してもらいたいと考える場合、亡くなってすぐに通夜と葬儀を済ませることとなり、遠方から来る親戚が間に合わないこともあります。
故人が献体に向かう前に式をした場合の葬儀の流れは以下の通りです。
- 葬儀・告別式の読経
- 別れ・花入れ
- ご遺体を受け入れ病院へ出棺
- 精進落とし
このように、出棺して向かう先が火葬場ではなく、大学に向かうに代わりますので、家族や親せきも式場で見送る形になります。
最近では献体への希望者が増えてきているようですが、本人と共に家族の同意を得ることが献体への登録の条件になりますので、多い事例であるとは言えないかもしれません。
仮に48時間以内に葬儀を行う事が不可能な場合は故人が献体に向かった後、遺体もお骨もない状態で通夜と葬儀を行う事も可能です。
ただ、菩提寺の場合、献体のため故人の遺体が無い事は説明しておかなくてはいけません。また、親族にも同様の説明が必要になります。しかし、葬儀屋さんは遺体が無い状態でも問題なく式をおこなってもらえます。
献体から戻ってきてからの式という方法もあります。献体から戻ってくるときは、火葬されお骨になった家族のもとへと戻ってきますので、必然的に骨葬になります。
しかし、献体から戻ってくるのは1年~3年と言われていますが、具体的にいつ帰ってくるかはわかりません。
まとめ
先に火葬を済ませておく骨葬を選ぶ理由は家族によっていろいろです。来てくれた人に説明ができる理由もあれば、説明するのも辛い理由もあります。
特に事故や事件であった場合は、家族が話そうとしない限り、そっとしておくことも優しさです。
最近では献体のためにご遺体がないケースもあります。献体の場合は大学側が火葬してくれます。
ただ、火葬だけでなく葬儀も行ってくれると勘違いしている人もいるようですが、間違った情報です。
大学側がしてくれるのは火葬までですので、しっかり説明を受け理解したうえで登録することをおすすめします。
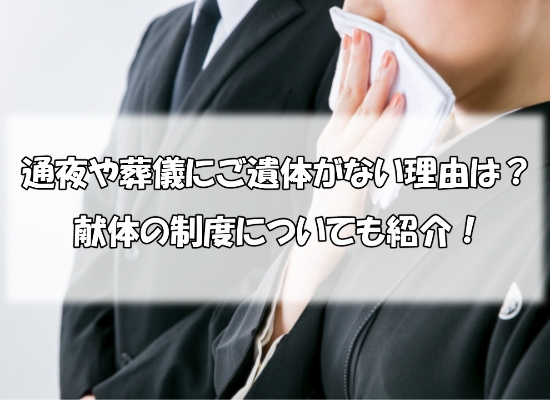


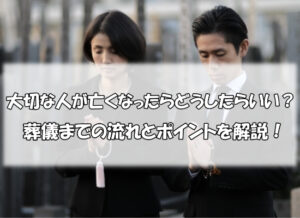
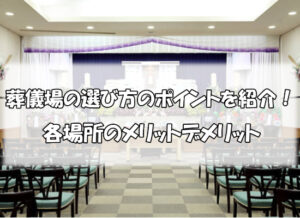
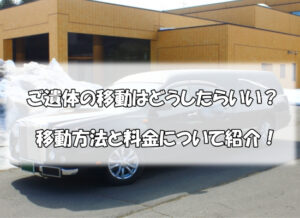
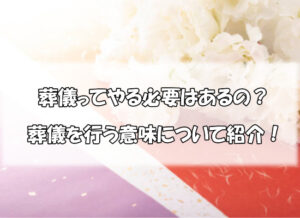
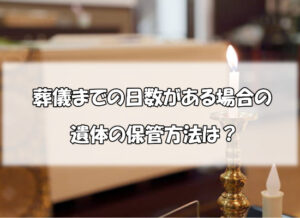
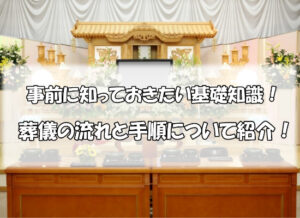
コメント