「急に訃報があり、葬儀や法事に参列しなければならなくなった!」
こんな経験がある方は多いのではないでしょうか?社会人になると今まで以上に人との付き合いが増え、葬儀やお通夜に参列するなんて機会が増えてきます。
学生時代は制服を着て参列したら問題ありませんでしたが、社会人になるとそういうわけにもいけません。
しっかり大人として恥ずかしくない服装をしなければなりません。間違っても目立つ格好で行かないようにしましょう。
「礼服は持っているから葬儀の際も大丈夫!」
そう思われた方は数珠もしっかりと持っていますか?
礼服は持っているけれど数珠はまだ用意していないなんて方も実は多いんです。
持っていたとしても、間違えて男性が女性用の数珠を持っていたりしませんか?
ということで、今回は数珠の葬儀マナーについて紹介させていただきます。
お通夜や葬式、法事、お墓参りの時に手にする数珠の正しい選び方から持ち方、そして、いまさら聞けない数珠の知識についてご紹介します。
葬儀用の数珠の正しい選び方

数珠を知らないという方や見たことがないなんて方はほとんどいないと思います。ただ、知っているという方でも数珠には種類あるということ知らない方が多いんです。
数珠には、「本式数珠」と「略式数珠」の2種類があり、購入する際はどちらにするかを選ぶ必要があります。
また、男性用と女性用があるので、男性が間違えて女性用を着けたりしないように気をつける必要があります。
略式数珠について
まず、「略式数珠」について紹介させていただきます。略式数珠というのは、宗派を選ぶことなく全ての宗派が使うことのできる一重の数珠の事です。
「片手念珠」と呼ばれることもあります。「本式数珠」と比べてコンパクトで持ち運びも便利なので「略式」と名前が付いています。
初めて数珠を購入するという方はこの略式数珠を購入するのがオススメです。
その理由は、こちらを選んでおくと全ての仏式葬儀で使うことが出来るからです。こだわりのない場合は略式数珠を選んでおくことが無難と言えます。
本式数珠について
次に、「本式数珠」というのは仏教の宗派ごとに決められている形式の数珠で、自分の宗派によって選ぶ二重の数珠の事です。「正式数珠」と呼ばれることもあります。
この数珠は108の玉数で出来ており、格式高い数珠といえます。自身の宗派がわかり、決められている形式の数珠がわかるようであれば本式数珠を購入してもよいでしょう。
若い時には略式数珠を使い、年齢を重ねたら本式数珠へ格上げをするなんてケースもあるようです。
他にも、自分の親族の葬式や法事の際には本式数珠を使い、それ以外の知人友人の葬式には「略式数珠」を使うというように使い分けるのもOKです。
葬儀用の数珠の男性用と女性用の違いについて

略式数珠と本式数珠の違いがわかったら、次は男性用と女性用の違いを理解しましょう。
ちなみに、私たちが普段使っている数珠のほとんどは略式数珠です。略式数珠には男性用と女性用があり、一番の違いは玉の大きさです。
| 男性用 | 女性用 | |
| 玉の大きさ | 10~12㎜ | 6~8㎜ |
男性用と比較すると女性用は一つ一つの玉が小さくサイズも小さいです。数珠を持っているという方は一度数珠のサイズを確認してみましょう。
次に、玉の数ですが男性用の略式数珠では本式数珠の108玉の半分の54玉、四分の一の27玉のものもありますが、22玉20玉のものも多いです。
男性用女性用ともに、石やガラスのカットは好みのものを選んで大丈夫で、マナー違反になることはありません。
葬儀用の数珠の選び方を紹介!色や素材には決まりがある?
次に、数珠を選ぶときのポイントについて紹介させていただきます。
数珠を選ぶときはどんなものを選んだら葬儀のマナー違反にならないのでしょう?
色について
実は、数珠の色や素材については特に制限がありません。服装の場合は明るい色はダメですが、数珠の場合は好みの色を選んで問題なく、マナー違反になることもありません。
年齢が若い時は明るい色で、年齢を重ねたら暗い色にしなくてはいけないなんてことはないです。ですので、安心して選んでくださいね。
材料について
数珠の材料には菩提樹の実や水晶、サンゴ、真珠などがあります。天然石を使用した数珠を選ぶ際には、それぞれの石に意味があると言われているので、確認してから購入するとよいでしょう。
数珠には房がついていますが、略式数珠の場合はどんな形のものを選んでも問題ありません。
最も一般的な形は「頭付房」と呼ばれています。もし、初めて購入する場合はこの形の物を選んでおくと良いでしょう。
葬儀用の数珠の正しい持ち方とマナーを紹介

葬儀の際に欠かせない数珠ですが、持ち方や使い方のマナーがあることご存知でしょうか?
使ったことはあるけれど、正しい使い方なんて知らなかったという方も多いはず。ということで、次は正しい使い方について紹介します。
数珠は葬儀中はずっと手に持つのがマナー
葬儀は宗派などによって違いはありますが、短くても1時間程度はかかります。
ですので、お葬式の最中は数珠をバックやポケット中に入れておいて、お焼香の時だけ取り出すなんて方もいるかもしれません。
しかし、数珠は葬儀の最中は基本的に手に持っておくのがマナーです。手に持つ際は房を下にして左手で持ちましょう。
合掌する際の基本的な持ち方は、左手に掛けて右手を添えるように合わせるか、合わせた両手に数珠をかけ親指で軽く押さえるようにします。
座ってお経を聞くような場合には左手首に掛けておきます。左手は仏の世界を表す手と言われていますので、数珠は左手に持つのが正式とされています。
数珠は一人一つ持っておくのがマナー
急なことで数珠が見つからない場合、一つの数珠を複数人で使い回すなんてケースが見られますがやめるようにしましょう。
数珠は念珠とも呼ばれ、持ち主を守る存在、分身ともいわれています。
ですので、家族などでも貸し借りはタブーとされています。一人ひとり専用の数珠を持っておくのが望ましいです。
そもそも数珠ってなに?数珠の由来の話

数珠は日本の仏教に古くから伝えられている大切な法具の一つです。
元々念仏やお題目、お祈りをする回数を数えるために使用したもので、8世紀ごろに仏教伝来とともに中国から伝わりました。
数珠は、念珠、珠数などとも呼ばれますが、全て数珠には違いがありません。
本式数珠の玉の数は108玉で、これは人間が持つ煩悩の数と言われており、煩悩を打ち消し、身を守るという願いを込めて数珠を持つようになったそうです。
数珠は法具の中でも唯一個人で持つことができることから、非常に尊いとされています。
数珠を身に付けることで、厄除け、魔除け、福を授かると言われています。
最後に
今回は数珠について葬儀マナーについて紹介させていただきました。数珠に種類があるなんて知らなかったという方も多いのではないでしょうか?
数珠を持つのはマナーの一つで、持っている方も多いと思いますが、持ち方や使い方まで知らなかったという方もいたかもしれません。
数珠は一人一つ持つのがマナーです。まだ持っていないという方はぜひ購入して下さいね。
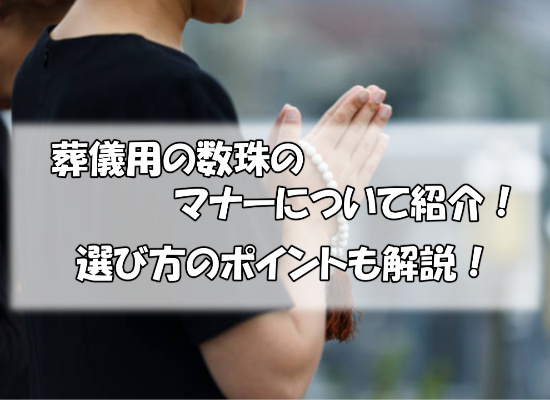

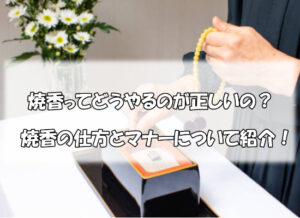
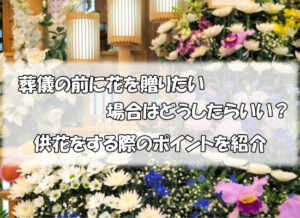
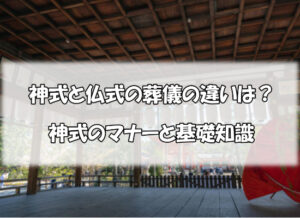
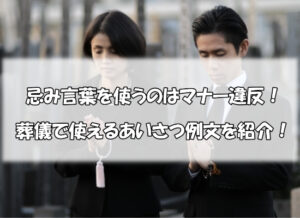
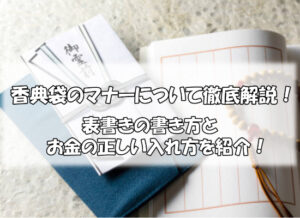
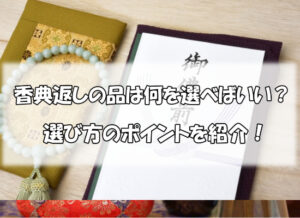
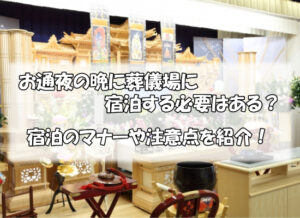
コメント