初詣に神社に行くというのはイメージがわくのに、葬儀の時は神社でするイメージってないですよね?
日本での葬儀と言われるのはお寺の住職が木魚をたたいている所や焼香をしている会葬者の姿をイメージする場合がほとんどだと思います。
ただ、葬儀=仏式だと思っている人は多いですが、葬儀は神式でも執り行われることがあります。
では、神式ってどんな内容か知っていますか?
もちろんお寺の住職は来ませんし焼香もありません。もし、縁のある人の葬儀に行ったとき神式だったらどうします?
ということで、今回は葬儀が神式だった時でも慌てないように神式のマナーや仏式との違いについて紹介させていただきます。
神式とは?仏式との違いは?

今では葬儀は仏式だと考えている人が多いので神式について知らない方が多いです。でも、実は神式は仏式よりも昔から日本で執り行われています。
神式と仏式の葬儀は次のような違いがあります。
住職でなく神官
お寺の住職が司式者として執り行われる仏式とは違い、神社の神官によって行われるのが神式です。
香典袋は白い水引の物で表書きは「御玉串料」「御神前」
香典に関しては違いがあり、表書きを「御玉串料」や「御神前」などを書くのが正式です。ただ、仏式でも使われる「御霊前」でも問題はありません。
香典袋は白の水引の物が正式ではありますが、用意がない場合は銀色の物や黒と白の水引の使用も可能です。
ただ袋自体は白の無地を選んでください。蓮の花が描かれたものは見た目が良いですが、蓮の花は仏の花です。
焼香ではなく玉串奉奠
玉串とは榊にシデという白い紙が付いたものです。
数珠は使用しない
念珠は仏式のみで使用します。
通夜・葬儀の呼び方が異なる
仏式では通夜と葬儀と言いますが、神式の場合は通夜祭と葬場祭と呼びます。また、通夜後の清めの食事のことも通夜ぶるまいと言わず直会(なおらい)の席と言います。
神官の入退場の際や玉串奉奠の際に雅楽を流す
仏式では僧侶がお経を唱えてくれますが、神式では神官が執り行います。神官が入退場する際や玉串奉奠の際には雅楽を流します。
服装は仏式と同じで大丈夫
神式で執り行うからと言って葬儀の際の喪服に違いはなく、仏式に着ていくものと同じという認識で大丈夫です。
神式の葬儀に参列する者としてはこれくらいの知識が入っていると慌てなくて済むかと思います。
神式の葬儀をする際に知っておくと良いことは?

神式と仏式では異なる点がいくつかあります。ですので、神式を執り行う場合は以下のことを知っておくと良いでしょう。
自宅の神棚を神棚封じする
神は死を穢れと言われることから、神棚を白い半紙で封じ穢れから守ります。半紙は家族でなく第三者に貼ってもらいます。葬儀屋さんが気づいて貼ってくれることが多いです。
故人の死装束は仏衣でなく神衣
同じ着物ではありますが、形が違い装備する小物も違います。
祭壇には神饌物が必要
祭壇には神にお供えする物(魚・餅・果物・野菜・酒・米・卵・乾物など)を用意します。葬儀屋さんが手配してくれることが多いです。
位牌と戒名はない
神式では位牌はなく、それと同じ扱いの物が霊璽です。初めて見る漢字かもしれませんが、霊璽(れいじ)と読みます。先祖の御霊が宿るので覆いをし丁重に扱いましょう。
他にも神官に渡すお布施の表書きは「御榊料」「御神饌料」と書くことや、仏式でいう四十九日は「五十日祭」ことが異なります。
このように仏式と神式では考え方や呼び方、用意するものまで変わってきます。
神式の通夜と葬儀の流れと玉串奉奠のやり方

次は実際の式の内容についてです。通夜祭と葬場祭のそれぞれの式次第になります。司式者である神社によって流れが多少違います。
通夜祭
- 斎主入場
- 開式の辞
- 修祓の儀…斎主によって祓い清める儀式
- 遷霊の儀…故人の魂を霊璽に移す儀式
- 斎主一拝…斎主が神に祭典を行うあいさつをする
- 献餞の儀…神に神饌物をお供えする儀式
- 祭詞奏上…仏式でいう読経にあたる
- 玉串奉奠…斎主→喪主→親族→一般の順番で行う
- 撤饌の儀…神饌物を下げる儀式
- 斎主退場
- 閉式
葬場祭
- 斎主入場
- 開式の辞
- 修祓の儀
- 斎主一拝
- 献餞の儀
- 祭詞奏上
- 玉串奉奠
- 十日祭祭詞奏上※仏式で繰り上げ初七日を行うように、繰り上げ十日祭を行うことがある
- 撤饌の儀
- 斎主一拝
- 斎主退場
- お別れの儀…故人と最後のお別れをする
このように式は行われます。式の中で何度か「御起立ください」「御低頭ください」と声掛けをされます。「御低頭」は文字にすれば分かるように軽く頭を下げることです。
では式の中に出てくる玉串奉奠(たまぐしほうてん)とはどのように行うのかですが、玉串奉奠は次のように行います。
- 神官の前へ行き喪主と神官に一礼
- 神官より玉串を受け取る(玉串は葉を左に両手で受け取る)
- 玉串を時計回しに回転させ葉が自分側、茎が祭壇側の向きで台に供え
- 2礼2拍手1礼する(この時の2拍手は音が鳴らないよう注意)
- 神官と喪主に一礼
玉串を奉奠する際には故人への思いを込めて供えます。神社に参拝に行く時と同じ2礼2拍手1礼をするのですが、拍手は音を出さないのが作法でこれを「しのび手」と言います。
神式における葬儀後の供養
仏式でも初七日や四十九日の法要があるように、神式においても法事に当たる供養の儀式があります。
神式ではその供養が翌日から始まります。翌日祭と呼ばれる供養ですが、こちらは家族で執り行うことが多いです。
帰幽の日から数え10日・20日・30日・40日・50日と、10日ごとに行う毎十日祭、帰幽の日から数え100日目の百日祭、帰幽から数え1年目の一年祭があります。
翌日祭・毎十日祭・百日祭・一年祭を霊前祭と言われ、五十日祭と一年祭をご親戚も集め特に丁重行います。
五十日祭が仏式でいう四十九日にあたり、五十日祭の翌日清祓を済ませることでひと段落付き、神棚の半紙を外すことができます。これで「忌明け」になります。
一年祭以降は三年祭・五年祭・十年祭と式年祭が行われます。こちらはご親戚も集め、清払の儀・祝詞奏上・直会を行います。
仏式の法事とは違い、供養の儀式は神社で行うことはありません。自宅または葬儀を行ったような貸し式場で行うこととなります。
火葬場と一緒になっている会場を使って葬儀をした場合、法事などでは借りることができない場合があるので確認が必要になります。
直会での料理の内容や出し方などに決まりはなく、仏式とも変わりはないようです。しかし喪家は火を使わず食事を用意するとも言われているので、仕出しなどを利用し直会の席を用意すると良いでしょう。
また直会は神饌として供えたものを皆で食べることとされているのですが、肉や魚も備える事が可能ですので、直会の食事に使用することも問題ありませんので安心してください。
まとめ
仏式が葬儀のやり方として一般的と思う方は多いかもしれませんが、初詣で神社にお参りに行ったり七五三で参拝する日本人にとって、実は神様という考えは慣れ親しんでいます。
神式の葬儀に参列をしたことが無いからビックリしてしまうだけで、お祓いをされるときに頭を下げるなど動作は慣れているでしょう。
「御低頭ください」と言われてキョロキョロやり方が分からないという人は意外といないのです。
玉串奉奠のやり方は会場でも教えてもらえますので、安心して縁ある人への供養をされてください。
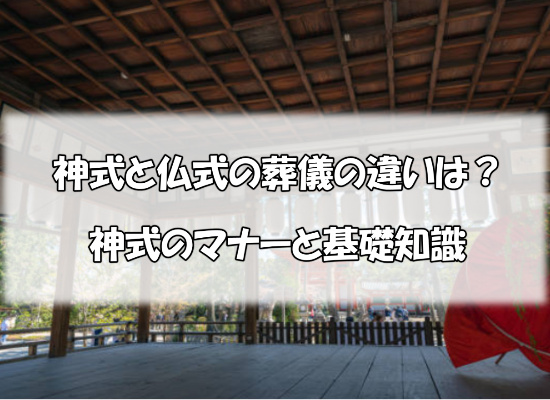


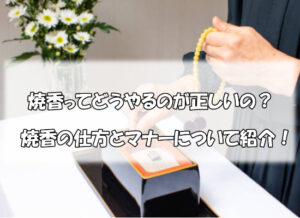
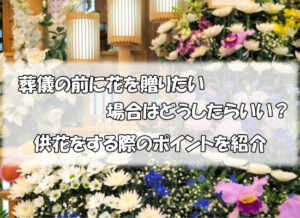
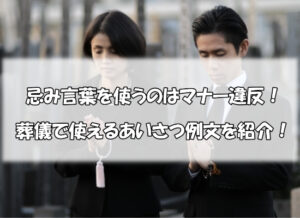
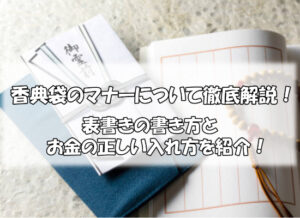
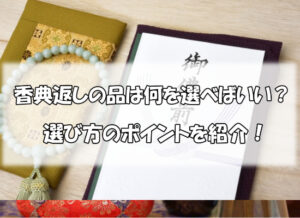
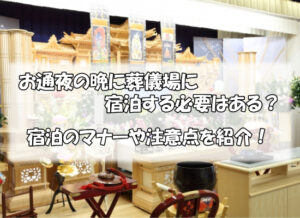
コメント