求人サイトをみるといろんな仕事を目にすると思います。事務や営業など様々な仕事がある中で葬儀の仕事を目にしたことはありますか?
仮にあったとしても、葬儀の仕事と言われ仕事内容を明確に思い浮かべることができる人はどれくらいいるでしょう。
葬儀に参列したことのある人は葬儀式場にいて案内や司会などをする人かな?と思い浮かぶかもしれません。
あるいは家族の葬儀をしたことがある人は、葬儀の打ち合わせをする仕事?なんて思うかもしれません。
仕事内容としてはどちらも正解です。でも、もちろんそれだけが仕事内容ではありません。では実際に葬儀屋さんはどのような仕事をしているのかを紹介させていただきます。
葬儀社の仕事内容を紹介!

葬儀に行かれたことが無い人が、葬儀と聞くとイメージは夕方から通夜が執り行われ、翌日葬儀告別式が行われているという事くらいではないでしょうか。
私自身も葬儀とは実際に働くまでは無縁でしたので、これくらいのイメージしかありませんでした。
では実際に葬儀屋さんはどのような仕事をしているのか紹介させていただきます。
電話対応
葬儀の依頼の電話を受けたり、既に決まっている葬儀に対する供花の注文や日程の確認・式場の場所などの問い合わせに対応します。
病院へのお迎え
葬儀社によっては寝台会社に委託している場合もありますが、依頼がきて病院に故人を迎えに行くのも葬儀屋さんの仕事です。
病院や施設によっては他の患者さんに分からないように白衣を着用し建物内に入ることもあるくらい気を遣う仕事内容です。
故人へのドライアイスの処置
故人への化粧などは納棺師の仕事にはなりますが、納棺式が執り行われるまでの間体の腐敗が進まないようドライアイスを当て、それが見えないように整えます。
葬儀まで日にちがあいてしまう場合は、何度か取り換える作業が必要になります。
打ち合わせ
通夜・葬儀を執り行うための細かいことを決めていきます。火葬場の予約などの作業もあります。
発注業務・事務作業
打ち合わせで決まった飾りのお花屋や返礼品・料理など取引業者への発注や打ち合わせをします。
またお礼状などの作成・問い合わせに対応するための地図や供花の注文書の作成を行います。
また菩提寺だった場合、お寺と連絡を取ったり必要に応じて塔婆や位牌をお寺に届けに行ったりもします。
式場準備
控室の準備や式場の準備祭壇の飾りつけ、供花の名前確認など通夜・葬儀と滞りなく進むよう入念に準備を行います。
通夜・葬儀進行
大きい式だとプロの司会者が入ることもありますが、基本的には葬儀屋さんが司会を行います。焼香の案内や館内の案内や受付の説明などを行います。
火葬場の案内
式場を出棺したらそのまま家族とともに火葬場に行き案内をします。火葬場の人が案内をすべてやるわけではなく、葬儀社の者が対応することもあります。
精進落としと解散の進行
食事前のあいさつや解散の締めなどの進行も行います。
館内片付け
次の葬儀が入った時にすぐに準備ができるようにしておく必要があります。
このような形で様々な仕事を行わなければいけないので、式のある日は朝から通夜の日は夜遅くまで仕事があります。
葬儀がない日は暇なの?葬儀がない日の仕事内容を紹介

上記のように式が入っている日は休む暇なくバタバタしていますが、葬儀は毎日あるというわけではありません。
では葬儀がないときは何をしているのでしょう?
葬儀場の設備の点検や清掃
葬儀社の従業員は依頼が入った時にスムーズに打ち合わせができるよう打ち合わせ書類などをそろえたり、館内の設備の点検と掃除を行っています。
葬儀場の営業
また、葬儀の仕事は表立ってうちの式場を使ってくださいと営業をかけられる立場ではありません。
ですので、チラシのポスティングを行ったり、事前に相談に来たり館内の見学に来た方の接客や以前利用してくれた方への後フォローなどが主な仕事になります。
葬儀の練習
入社して間もないスタッフに関しては、焼香案内の練習や各進行の声掛け練習をおこないます。
案内や進行がスムーズでないと時間内に全員の焼香を終わらせることができなかったり、たたでさえ慣れない葬儀という場で緊張気味になり動きが遅くなる参列者に、慣れないスタッフが接すると参列者がどうしていいか分からず動けなくなるのです。
司会の練習も行うこともあります。葬儀で使う言葉は普段使い慣れている言葉遣いとは違うことが多いです。
そのため、司会の際に噛んでしまったり故人の名前を間違えてしまったり、弔電の漢字が読めないなんてことにならないためにも練習が必要です。
資格取得の勉強
実は葬儀の仕事にも厚生労働省認定の葬祭ディレクター技能審査という資格があるのをご存じですか?
その試験に向けて勉強をあいている時間にしている人もいます。ちなみにこの試験は筆記だけでなく実技試験もあります。
葬儀屋は24時間営業

葬儀屋さんの仕事は昼間だけではないの?友引の日は休みじゃないの?
通夜は夕方からだからお昼くらいから出社してるんじゃないの?とか友引の日は定休日なんでしょ?なんて思われがちですが、全く違います。
葬儀屋さんは365日24時間休みはありません。なぜかというと、それは亡くなる人は24時間365日朝も夜も休日も祝日も関係なく亡くなり、葬儀の依頼が来るからです。
夜中亡くなったから朝まで待って葬儀の依頼をなんてことはありません。
だからどの葬儀屋さんも夜中でもスタッフが常駐、もしくは自宅待機という形で会社の電話を受けるような仕組みになっています。
もちろん毎日依頼が来るわけではありません。いつかかってくるか分からない電話をすぐに取れるようにしています。
宿直業務という形をとり、会社で仮眠を取りながら待機する会社もあれば、自宅待機という形をとる会社と様々ですが、自宅待機のやり方を採用している会社は、採用の際に1時間以内の距離に住んでいる人など条件が付けられていることが多いようです。
友引はよく友を引くからとか言って葬儀はやらないんでしょ?定休日なの?なんて思っている人も多いですが、先ほども書きましたが、依頼や問い合わせの電話はあるんです。
そして友引は火葬場が休みだから葬儀ができないだけで、通夜はできるのです。
しかも友引でも休みではない火葬場も数多くあるんです。ですのでスタッフは順番に休みますが葬儀屋さんは休みはありません。
年越しやお正月も休みがないのですから休みが大切って人には向かない職業かもしれませんね。
まとめ
今回は葬儀屋さんの仕事内容について紹介させていただきました。普段葬儀社の仕事を知る機会はなかなかないと思います。
もちろん、どんな職業でも分からない仕事内容はあるとは思いますが、葬儀屋さんは事務作業から案内などの立ち仕事や司会など仕事の幅が広いです。
また、24時間で定休日がない事にも驚かれるのではないでしょうか?
突然の訃報がいつ起きるかなんてことは誰にもわからないので、いつでも24時間対応しているのが葬儀社なんです。
生の為に働いている職業の人にも感謝する必要がありますが、死にかかわる職業の人にも感謝をしたいものです。
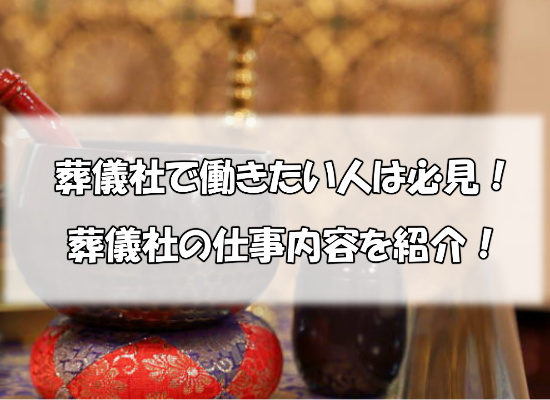
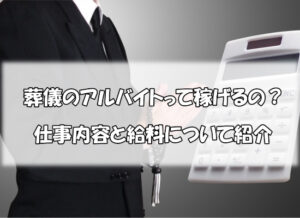
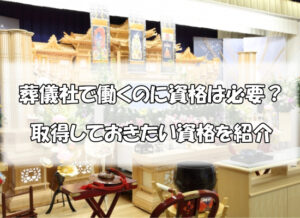
コメント